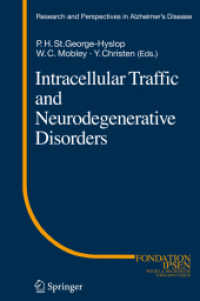出版社内容情報
学校に行かないことが不登校として「問題」だと言われるのはなぜか。身体を壊しても打ち込んだ部活動が「美しい」のはどうしてか。多年にわたり教育相談に従事してきた著者がみた日本社会、はなはだしくは過労死にもいたる「皆勤」の空気と、それに囲まれた現代学校の姿を浮き彫りにする。
内容説明
学校に行かないのは「問題」?身体を壊しても部活動に打ち込むのは「美しい」?教育現場や社会を取り巻く「皆勤」の空気と、ワークライフバランスを教育相談の第一人者と考える。
目次
「休むこと」についての意識は変わってきたのか?
第1部 日本社会と「休むこと」(「休むこと」についての意識変化;日本社会の働き方;長時間労働と勤務間インターバル;教員の場合)
第2部 スポーツ界と「休むこと」(高校野球と「休み」;近年のスポーツ界等の動向;高校野球の今後)
第3部 学校教育と「休むこと」(皆勤賞という存在;「出席停止」という規定;入学試験における「欠席」;学校の部活動におけるガイドライン)
第4部 「休むこと」について考える(「欠席」からみた戦後学校教育;具合が悪くても休まない学校教育;「長期欠席」に注目しなくなった学校教育;「休むこと」についてのルールと無知学;学校教育における「しつけ(躾)」)
欠席と遅刻
著者等紹介
保坂亨[ホサカトオル]
千葉大学名誉教授・教育学部グランドフェロー。1956年生まれ。東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得中退。東京大学教育学部助手(学生相談所専任相談員)、千葉大学教授等を経て現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
katoyann
TAK.I
てくてく
AyaZ
お抹茶
-
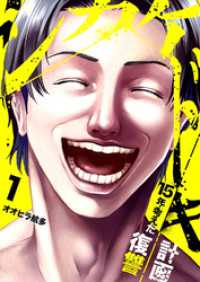
- 電子書籍
- シカケドキ~15年考えた復讐計画~1 …
-

- DVD
- ウルフ・タウン