目次
看護師のエラーが犯罪となるとき
なぜ公正な文化が必要なのか?
失敗をとがめるべきか許すべきか?
報告の重要性と報告のリスク
情報開示の重要性と情報開示のリスク
すべての失敗は同等か?
後知恵による責任追及
悪いことをしていないならおそれる必要はない?
検察官がいなければ犯罪は存在しない
裁判は安全を害するか?
公正さを追求する裁判の関係者たち
公正な文化に対する三つの問い
「個人かシステムか」から「システムの中の個人」
公正な文化を構築するためのアプローチ
著者等紹介
デッカー,シドニー[デッカー,シドニー][Dekker,Sydney]
ルンド大学教授、Ph.D.。専門はヒューマンファクターズ(人間工学)。ヒューマンエラー、システム安全、失敗に対する刑事罰の可否などに関する多くの著論がある
芳賀繁[ハガシゲル]
立教大学現代心理学部教授、博士(文学)。京都大学大学院修士課程修了後、鉄道労働科学研究所、鉄道総合技術研究所、立教大学文学部心理学科などを経て、2006年4月から現職。JR西日本「安全研究推進委員会」委員、日本航空「安全アドバイザリーグループ」メンバー、中央労働災害防止協会『安全と健康』編集委員などを兼任。専門は産業心理学、交通心理学、人間工学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
toko1968
5
航空の視点から読むと尤もなことなのだが、今の日本ではこのようなことが全く実現できていない。事故が起こるとマスコミはパイロットミスと騒ぐし、専門家ではない警察の捜査が優先され原因調査は後回し、司法までもが誰か規則に違反した人間をスケープゴートにして有罪判決を出して終わり。結局、再発防止には何の役にも立たないのが現実である。 明らかな悪意や過度の怠慢を持って事故を起こした場合を除き、責任追及より再発防止を優先する考え方ができる日は日本に来るのだろうか。無理だろうなぁ。2018/11/20
ぞだぐぁ
4
ヒューマンエラーの責任を起こした個人に押し付けるのでは別の人によって同じ事故が再発してしまうだけなので、構造的なものから直していくべきだという本。日本でも福知山線の事故で運転士の日勤教育や速度安全装置の不備などが挙げられるようになったが、海外でも組織の自己保身のために生贄にされた人はやっぱりいて、それでは問題の根本的な解決にならないってこと。2019/03/02
メルセ・ひすい
4
☆チェズレイ・サレンバーガー・・ そうです!エンジンが停止したジェット旅客機を冷静・沈着に飛行術を駆使して、ハドソン川に着水!⇒一躍・英雄に・・ その時読んでいたのが、本書『ジャスト・カルチャー』原題である。 ブルームバーグ市長は図書館から機長が借りていた、本書を市費で弁償した。 専門職がエラーをどこまで・・・ 暗い話だが・・ 運ばかりを当てにはできないんです。 今、人の命を預かる職からの逃避が・・・ 2010/01/12
nabechiki
3
ヒューマンエラーを原因ではなく症状と考えるべき。原因の説明責任を求めて罰しても、組織に不安が生まれ、より質が下がるだけ。そもそもそのエラーが悪質かどうかは客観的には判断できず、どう境界線を引くかは組織の質に委ねられる。国家レベルの話になると、司法がどう境界線を引くかの難しい話になるが、組織レベルで考えると、いかに関係性を保ち、報告を罰せずに奨励し、個人個人が改善している感覚を得られる状態を保つことが大切ということか。2017/03/26
焼きそばん
3
失敗から学ぶという本がもてはやされて私も何冊も読んだが、如何に深層原因を突き止めるのが難しくなってしまうのかという側面と、裁判において原因を知りたいということに対して、裁判の仕組みそのものがそれを望んでいないのでそれを明らかにすることができないということを実例を挙げて丁寧に書かれています、事故は一人の不注意に結論を落とし込みやすいですが、その周りでそれを助長していたり、善意でその仕組みの問題を改善しようと報告した人間が悪者になってしまうという普通ではあり得ない現実がそこに書かれていました。2016/09/22


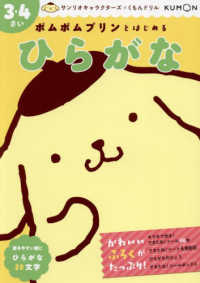
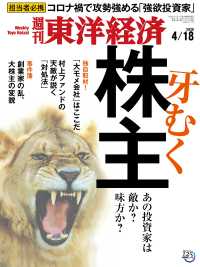
![ハンドルであそぼ〓 えほん [バラエティ]](../images/goods/ar2/web/imgdata2/43307/4330784173.jpg)


