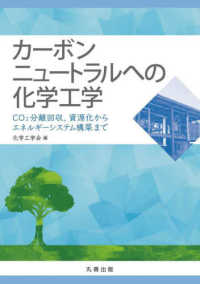内容説明
日米の金融危機における教訓とは。日本の1990年代の金融危機の要因と影響を、膨大な銀行と企業のミクロデータを用いて詳細に分析するとともに、アメリカ金融危機の考察も踏まえ、金融システム安定化への政策課題を提言する。
目次
第1部 金融危機の要因と銀行行動(不良債権問題はなぜ長期化したのか;不良債権問題はどのように解消されたのか;銀行の合併は効率性と健全性を改善させたか)
第2部 金融危機と実体経済(銀行の健全性は中小企業の設備投資に影響するか;金融危機はマクロ経済の生産性を低下させるか)
第3部 金融危機と経済政策(銀行のバランスシートは金融政策の有効性に影響するか;金融政策は企業の流動性制約に影響するか;日米の金融危機から得られる教訓は何か)
著者等紹介
細野薫[ホソノカオル]
1961年京都府生まれ。1984年京都大学経済学部卒業。1990年ノースウェスタン大学経済学修士。経済企画庁(現内閣府)、大蔵省(現財務省)、一橋大学経済研究所、名古屋市立大学経済学部などを経て、学習院大学経済学部教授、博士(経済学)(一橋大学)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。