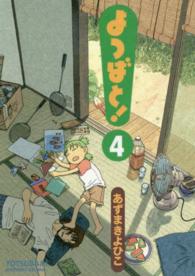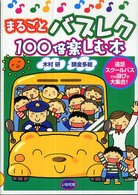出版社内容情報
「行政法総論の改革」プロジェクトを10年にわたって主宰してきたシュミット‐アスマン教授の主著の翻訳。
内容説明
発展線を浮き彫りにし、諸作用の連関を明示し、変更が必要な点について省察することも、行政法学には課されている。そして、市場を規整する新たな形式や、行政活動のヨーロッパ化のもたらす諸課題を、伝統的な法解釈学と折り合うよう調節しなければならない。本書は、こういった今後に向けた課題領域の方に専念したものである。
目次
第1章 行政法の体系と体系の構築
第2章 法治国と民主政を選択する憲法決定
第3章 行政の任務と行政法各論の役割
第4章 制御とコントロールの間で活動する行政の自立性
第5章 組織としての行政と組織法の意義
第6章 行政の活動システム:形式、手続、法関係、原則
著者等紹介
シュミット‐アスマン,エバーハルト[シュミットアスマン,エバーハルト][Schmidt‐Assmann,Eberhard]
1938年生。ハイデルベルク大学名誉教授
太田匡彦[オオタマサヒコ]
1971年生。東京大学大学院法学政治学研究科助教授
大橋洋一[オオハシヨウイチ]
1959年生。九州大学大学院法学研究院教授
山本隆司[ヤマモトリュウジ]
1966年生。東京大学大学院法学政治学研究科教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
フクロウ
4
立憲君主政下で培われた行政法理論は、立憲民主政下では使えない部分も多いはずである、という直観から、新しい行政法の基礎づけを探している過程で見つけた(もちろん木庭顕『笑うケースメソッドⅡ 現代日本公法の基礎を問う』と山本隆司『判例から探究する行政法』経由ですが。笑)。問題意識はドンピシャで、結局、立憲民主政下での行政法はブレーキ(法治国原理)だけでなくアクセル(民主政原理)にもなる必要があり、それぞれの要請を踏まえつつ、具体的場面の規律を考えていく必要がある。2025/10/14
しろ
0
興味があるところのみ。①法治国原理と民主政原理という憲法上の基本原理と②行政の諸任務(行政法各論)を基礎に、システムとしての行政法の構築を試みている。逐語訳のせいか、はたまた己の能力不足のせいか、とにかく読みにくかった。先に訳者あとがきを読んでから本論に移ったほうが、内容を理解しやすいように思われる。2013/10/21