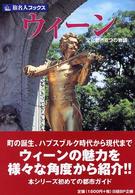出版社内容情報
古代国家の崩壊のなか抬頭してきた鎌倉武士団を大きくクローズアップさせ,時と状況を重視する戦闘者の行動様式のうちに,主体的エートスの創出を見る.幕末・維新の志士における「忠誠と反逆」の歴史的源流を突きとめた,未公開の注目すべき論稿.
内容説明
坂東武者の強烈な名誉感と自負心、そして主従のちぎり。時と状況を重視する戦闘者の行動様式のうちに、自生的な「主体」の萠芽をさぐった、未公刊の講義。さらに、神道から『神皇正統記』におよぶ。主体的エートスの形成。
目次
第1章 日本思想史の歴史的所与
第2章 武士のエートスとその展開(初期武士団の発生と構造;「武者の習」もしくは「弓馬の道」(弓矢の道)の形成
武士のエートスの概念的洗練(合理化)
変容と分化
戦国武士道の形成)
第3章 神道のイデオロギー化(神仏習合の思想的過程;神道理論の発展;『神皇正統記』の思想的位置)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
Ikkoku-Kan Is Forever..!!
2
【四冊】丸山はまず、「religion」の語源が「結び」であることを指摘し、「超越者と人間の関係がそのまま人間関係に跳ね返えり宗教倫理を形成するもの」として「宗教」を定義する。丸山はその上で、日本思想史における超越者との出会いの淵源を仏教に求め、「鎮護国家」として始まった日本の仏教が、鎌倉仏教において聖俗関係の再定義を迎える経緯を叙述。それは、徐々に仏法・王法相依観念が崩壊し、聖なるものの内面化による主体形成(エートスの顕現化)というプロセスである。(『日本政治思想史研究』のシェーマの拡大)2017/06/10
半木 糺
1
1965年度に東京大学法学部の「東洋政治思想史」にて行われた講義をまとめたもの。「日本思想史の歴史的所与」「武士のエートスとその展開」「神道のイデオロギー化」の三篇を収録している。特に分量が多く割かれているのは「武士のエートスとその展開」である。丸山眞男は西欧近代型の「主体」をいかに日本思想史上に見つけ出し得るか。あるいはそれをどのようにして戦後日本の中に位置づけるか、を主な問題意識としていた。結果、丸山は武士のエートスの変遷と変容を「主体性」というテーマで捉えようとしている。2015/03/03
kotsarf8
0
武士のエートスについて論じた1965年講義。この年は珍しく原型論が語られなかった。武士のエートスがいわゆる主体性の確立まで至ったのかは疑問符である。2012/03/17
-

- 洋書
- Ulica Nowa 3