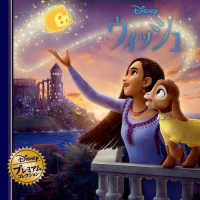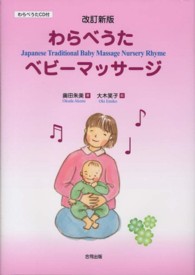出版社内容情報
1956年の経済白書で「もはや戦後ではない」とうたわれ,同時期,日本政治研究は新しい段階に入った.高度成長は日本の政治と政治学に何をもたらしたのか.本書は,高度成長期の主要業績を取り上げ,その内容と分析方法を考察する.『戦後政治と政治学』の続編.
内容説明
激変した日本政治をどのように捉えたのか。高度成長期の20年の日本政治について多様な分析が試みられた。松下圭一、田口富久治、升味準之輔、高坂正堯、三宅一郎…の主要業績を取り上げ、高度成長が日本の政治と政治学にもたらしたものは何かを問い直す。
目次
第1章 大衆社会論の登場―松下圭一
第2章 アメリカ政治学の受容と理論的実証分析の開始―田口富久治
第3章 利益政治による自民党支配―升味準之輔
第4章 保守外交の再評価―高坂正堯
第5章 投票行動の行動論的研究の登場―三宅一郎
第6章 政党研究への新規参入―カーチス、堀幸雄
第7章 エリート論的日本政治解釈―三沢潤生、伊藤大一
第8章 保守政権下の産業政策―大原光憲・横山桂次、米商務省
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
わび
2
『戦後政治と政治学』の続編。戦後初期に支配的であった近代主義(講座派)的解釈が高度成長によって説得力を失っていく中で、いかなる枠組が模索されたのかを、主に8人の政治学者とその研究について検討を加える。研究の選択があくまで著者の関心に基づいており、一学問の歴史として読むのがどこまで妥当かという問題は前著にも増して感じるが、切れ味鋭く論評していくスタイルは読んでいて気持ちが良い。中でも、吉田茂論を中心に鋭い指摘をしながらも、畏敬の念が溢れ出てる高坂正堯についての章は出色に感じる。2020/07/30
Haruka Fukuhara
1
面白いか面白くないかというと大して面白くない本だと思ったけど、結構評価が高いのは類書がないからか。高坂正堯の項は面白かった。2017/03/16
挙党協
0
≪一九八〇年度以降、多元主義の登場とともに、政策過程の研究に多くの蓄積が見られるようになったが、その分だけ、残念ながら官庁組織それ自体を(とくにエリート主義的)観点から研究する業績は、少なくなっている。その作業は、もっぱらジャーナリストに委ねられているといっても過言でない程である≫(p.164) 本書は著者の戦後政治学レビューのひとつだが、様々「そういうことが聞きたかった!」という言葉がさらりと記されている。学習の手がかりにしたい。2017/03/06
denken
0
「戦後政治と政治学」の続き。松下圭一やら高坂正堯のような,現内閣の重要人物に影響を与えた人に対する論評あり。つまり菅と前原。2010/09/26
-

- 電子書籍
- おはよう21 2018年11月号