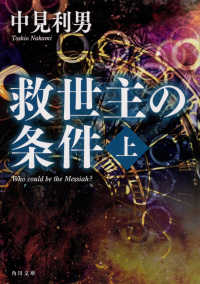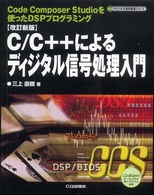出版社内容情報
20世紀の数学や物理学における概念の生成を、エピステモロジーすなわち科学認識論の系譜にある哲学者の議論から読み解き、場の量子論や非可換幾何学にまで通じる〈科学作品の解釈学的現象学〉を提唱する。科学的対象における概念と実在性の関係を問う大著。
目次
第1部 概念の哲学の系譜―フランス・エピステモロジーの中の数理哲学(哲学的方法論としての“概念の哲学”の導入―カヴァイエス;代数学における構造と操作性―ヴュイユマン;数学における操作と対象の双対性、ならびに経験―グランジュ)
第2部 自然科学の哲学的分析方法論と解釈学的現象学―エピステモロジーとリクール哲学の接続(純粋現象学から科学作品の現象学へ―リクールの“三重のミメーシス”からの接近;科学の解釈学的現象学の構築―概念生成への問いから実在性への問いへ)
第3部 量子力学のエピステモロジー―物理的実在性への問いとアナロジー(場の量子論の科学作品の現象学―量子論における代数的視点と幾何学的視点の干渉;物理学における反省的方法とエポケー、そして実在性の再把握―科学活動内部の現象学と解釈学;アナロジーによる物理的概念の運動と生成―量子論の構築におけるアナロジーの媒介機能)
第4部 非可換幾何学のエピステモロジー―弁証法による数学概念の生成と統一化への運動(現代数学における領域横断的な理論の発展―作用素環論の場合;現代幾何学における操作―対象の双対と概念の拡張―リーマン=ロッホの定理からアティヤ=シンガーの指数定理へ;数学の統一化へ向けての弁証法とアナロジー―A.コンヌの非可換微分幾何学の場合)
著者等紹介
原田雅樹[ハラダマサキ]
関西学院大学文学部教授。1967年生まれ。1990年東京大学理学部地球物理学科卒、2005年パリ第7大学(現パリ・ディドロ大学)大学院科学史およびエピステモロジー専攻博士課程修了。博士(科学史・科学哲学)。仙台白百合女子大学准教授、清泉女子大学キリスト教文化研究所教授を経て、2019年より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。