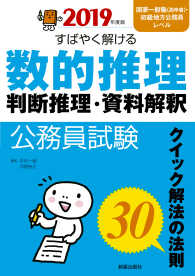出版社内容情報
子どもは教室で生きている,もがいている,考えている!--教室の中で火花を散らしている子どもたちの思考過程を,4つの傑出した授業実践を素材に,4人の教育学者が徹底解析し,新しい「授業の認知科学」の方向をさぐる.
内容説明
子どもは教室で生きている、もがいている、考えている。―教室の中で火花を散らしている子どもたちの思考過程を、四つの傑出した授業実践を素材に、4人の教育学者が徹底解析し、新しい「授業の認知科学」の方向をさぐる。
目次
1 子どもが表現するとき―作文における誠実さと真実さ(丹羽徳子氏の実践から;子どもにとって作文とは何なのか;討論)
2 子どもの納得世界を探る―算数の学習の場合(算数教育はうまくいっているのか;討論;算数が「わかる」ということ―ランパートの実験授業の考察)
3 子どもが生きる授業―有田和正氏の社会科授業に見る学習の分析(授業観察による学習過程の研究;学習過程モデルの再検討;討論)
4 授業で子どもの信念を変えることは可能か―仮説実験授業の場合(仮説実験授業「ばねと力」の授業過程;授業の評価と問題点;討論)
感想・レビュー
-

- 電子書籍
- 極上☆グラビアガールズ 松本さゆき v…