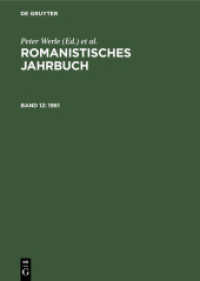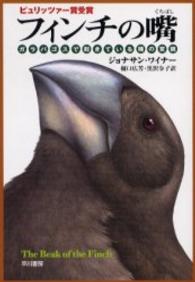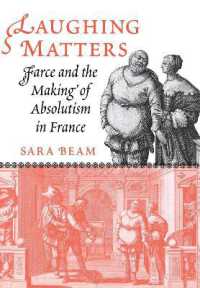出版社内容情報
近世都市江戸で暮らす人々の生態と風俗を紹介する。武士と町人が区分けされてそれぞれに生活していたため、江戸にはさまざまな顔がある。本書の江戸は「大江戸」と呼ばれ出した天明以降に設定し、富裕商人「魚河岸問屋の惣領」、長屋住人「本所割下水の棒手振」、上級武士「町奉行」、下級武士「南町奉行所の定町廻り同心」、さらには「大奥女中」と「吉原芸者」の6例をあげ、それぞれの仮想主人公の視点から江戸暮らしのそれぞれを紹介する。各層のモデルとなる人物が一日をどのように過ごしたかを、浮世絵などを駆使して構成。各層人の衣食住、慣習・掟の相違を取り上げ、同じ身分でも階層が異なればこれほど違った生活だったことを明らかにし、江戸という都市の多様性・多重性をあぶり出す。江戸のコツがわかる本、本書掲載の江戸知識で時代劇や時代小説が100倍おもしろくなる。
●序章 江戸の暮らし基礎知識
●第1章 富裕商人代表、日本橋大店惣領の24時間
●第2章 長屋住人代表、本所割下水棒手振の24時間
●第3章 上級武士代表、南町奉行の24時間(3000石取り)
●第4章 下級武士代表、定町廻り同心の24時間(30俵二人扶持)
●第5章 大奥女中の24時間
●第6章 吉原代表、吉原芸者の24時間
●巻末 【江戸の年中行事】【大江戸俯瞰図と江戸がわかる年表】
【江戸がわかる飛び切り20冊】
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
スリカータ
7
面白かった!べらぼうを観ていると花魁や吉原のことは何となく解って行くが、図解されるとスッキリわかる。江戸の長屋のコンパクトで簡素なことよ。押入れがないので寝具は衝立で隠していた。そして、頻繁に火事が起きるので造りは非常に簡素だという。井戸端会議という言葉は、水汲みに井戸に集まる主婦たちのお喋りが日常。お風呂というものは湯船ではなく、板敷の間にお水やお湯を汲んだ桶で身体を洗って拭いていた。処刑のページは残忍でサッと読み。2025/06/09
kaz
2
江戸時代の風俗等に関する本や落語、浮世絵の本等で断片的に知っている内容ではあるが、改めてビジュアルで当時の生活が確認でき、落語を聴く際のイメージがさらにクリアになる気がした。図書館の内容紹介は『18世紀になり、人口100万の巨大都市に成長した江戸。そんな「大江戸」に暮らすさまざまな身分・職業の人々の日常生活を通して、江戸の文化・流行・しきたりを紹介する』。 2022/11/12
ちえぞう
0
江戸時代に生まれていたらというシチュエーションで様々な身分の人の生活を描いた一冊。大河ドラマべらぼうの影響で図書館でついつい手にしたのですが、男性はお武家さま、女性は大奥勤めか遊女って極端な設定が中心。家康が作った江戸の町なので武家のしきたりとか、罪と罰のパートとか面白かった。不義密通が死罪とか放火犯は火あぶりとかパンチあったなぁ。2025/06/27
-

- 電子書籍
- GetNavi 2013年2月号