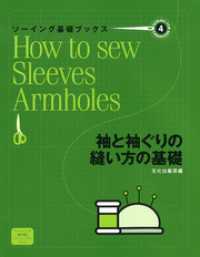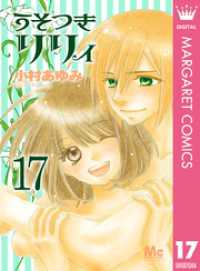出版社内容情報
一九五五年、京都大学の学術探検隊に同行し、西アジア諸国を歴訪した著者。その体験から生まれた視点により、対立ではなく平行進化として東西の近代化を捉え、〈中洋〉を提唱する。六〇年代にかけての東南アジア、アフリカ各国訪問を経て、比較宗教論へと連なる論考の集成に、著者の到達点を示す「海と日本文明」(二〇〇〇年)を増補する。
〈解説〉谷泰
内容説明
一九五五年、京都大学の学術探検隊に同行し、西アジア諸国を歴訪した著者。その体験から生まれた視点により、対立ではなく平行進化として東西の近代化を捉え、“中洋”を提唱する。六〇年代にかけての東南アジア、アフリカ各国訪問を経て、比較宗教論へと連なる論考の集成に、著者の到達点を示す「海と日本文明」(二〇〇〇年)を増補する。
目次
東と西のあいだ
東の文化・西の文化
文明の生態史観
新文明世界地図―比較文明論へのさぐり
生態史観からみた日本
東南アジアの旅から―文明の生態史観・つづき
アラブ民族の命運
東南アジアのインド
「中洋」の国ぐに
タイからネパールまで―学問・芸術・宗教
比較宗教論への方法論的おぼえがき
海と日本文明
著者等紹介
梅棹忠夫[ウメサオタダオ]
1920年(大正9)、京都市に生まれる。43年、京都大学理学部卒業。理学博士。学生時代の白頭山登山および大興安嶺探検隊以来、調査、探検の足跡は、ひろく地球上各地にしるされている。京都大学人文科学研究所教授、国立民族学博物館長を経て、同館顧問・名誉教授。京都大学名誉教授。専攻は民族学、比較文明学。94年、文化勲章受章。2010年(平成22)、死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
特盛
アメヲトコ
おやぶたんぐ
なかすぎこう
tuppo



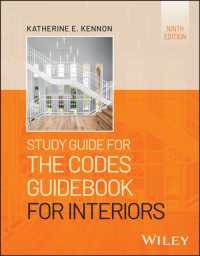
![恋するダイアモンド[1話売り] story14 花とゆめコミックススペシャル](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1697906.jpg)