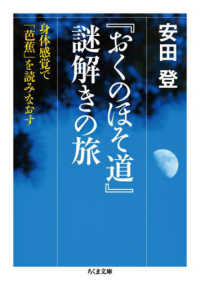出版社内容情報
シーボルトと遊女・其扇の間に生まれ、当時女性でありながら医学の道を志した楠本いね、「解体新書」翻訳を成し遂げた前野良沢、ロシヤ抑留中に種痘法を習得した中川五郎治など、後に著者によって長篇として描かれた人物を含む、日本近代医学の先駆者である十二人の医家たちの苦難の生涯を描く。
内容説明
「解体新書」の翻訳を牽引した前野良沢(『冬の鷹』)、日本最初の女性産科医・楠本いね(『ふぉん・しいほるとの娘』)、脚気病の治療法を開発した高木兼寛(『白い航跡』)…。江戸中期から明治初期に現れた、日本近代医学の先駆者たち十二人の苦闘の生涯を描く。著者による医家をテーマにした長編作品群の原点であり要となる短編集。
目次
山脇東洋―日本で初めて腑分を実見した医家
前野良沢―「解体新書」の翻訳を進めた中津藩の藩医
伊東玄朴―江戸屈指のオランダ医家
土生玄碩―新しい手術を積極的に推し進めた眼科医
楠本いね―シーボルトの娘で日本初の女性産科医
中川五郎治―日本における種痘法の祖
笠原良策―種痘の普及につとめた福井の医家
松本良順―初代陸軍軍医総監
相良知安―日本にドイツ医学を定着させた医家
荻野ぎん―日本最初の女医
高木兼寛―脚気病の治療法を実証的に開発した功績者
秦佐八郎―梅毒の特効薬を開発した細菌学者
著者等紹介
吉村昭[ヨシムラアキラ]
1927(昭和2)年、東京・日暮里生まれ。学習院大学中退。58年、短篇集『青い骨』を自費出版。66年、『星への旅』で太宰治賞を受賞、本格的な作家活動に入る。73年『戦艦武蔵』『関東大震災』で菊池寛賞、79年『ふぉん・しいほるとの娘』で吉川英治文学賞、84年『破獄』で読売文学賞を受賞。2006(平成18)年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ケンイチミズバ
yukision
k sato
スプリント
アメヲトコ