出版社内容情報
武士とは、何だったのか?
千年に亘る戦いの系譜を一冊に刻みつけた、驚愕の傑作歴史小説。
〈螺旋プロジェクト〉中世・近世篇。
負け戦の果てに山中の洞窟にたどり着いた一人の武士。死を目前にした男の耳に不思議な声が響く。「そなたの『役割』はじきに終わる」。そして声は語り始める。かつてこの国を支配した誇り高きもののふたちの真実を。源平、南北朝、戦国、幕末。すべての戦は、起こるべくして起こったものだった――。〈巻末付録〉特別書き下ろし短篇
内容説明
負け戦の果てに山中の洞窟にたどり着いた一人の武士。死を目前にした男の耳に不思議な声が響く。「そなたの『役割』はじきに終わる」。そして声は語り始める。かつてこの国を支配した誇り高きもののふたちの真実を。源平、南北朝、戦国、幕末。すべての戦は、起こるべくして起こったものだった―。“巻末付録”特別書き下ろし短篇。
著者等紹介
天野純希[アマノスミキ]
1979年生まれ、愛知県名古屋市出身。愛知大学文学部史学科卒業後、2007年に「桃山ビート・トライブ」で第二〇回小説すばる新人賞を受賞しデビュー。13年『破天の剣』で第一九回中山義秀文学賞、19年『雑賀のいくさ姫』で第八回日本歴史時代作家協会賞作品賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mae.dat
252
螺旋プロジェクト第3弾。外伝も含めて、各時代のエピソードに、イソベリ・ヤマノベの対立を混ぜ込んだ12話の短篇とも取れるのかな。中世・近世時代の千年近い時間を巡る争いの歴史。だから時間が飛び飛びも仕方ないですね。例えば、やっと戦国かと思ったら天正10年(1582年)。戦国時代の多くはすっ飛ばしですか。そうですか。ってなったもん。日本だけが特別なのでは無いのかも知れませんが、正に「武士(もののふ)の時代、武士の国」ですね。やっぱり、秀吉と家康の会話が楽しかったかな。強引さを含めて。【螺旋プロジェクト🧬】2025/02/07
きいたん
46
う~ん、うまい!いや、もののふに敬意を表し「アッパレ!」と言おうか。螺旋プロジェクト3作目は鎌倉~幕末約900年にも及ぶもののふ=武士達の物語。山と海の対立を歴史上の人物に当てはめ、その間を取り成す黒と青の瞳を持つ長老を超越した存在として使いこのように描くとは。史実をなぞる物語は正に戦いの歴史。だからこその緊張感が終始続き、一本の芯のように貫かれるもののふの魂。相容れない山族と海族、そして長老のチョイスが絶妙で、これが本当に事実なのではとうっかり思ってしまう程。螺旋プロジェクト全開で、次作が益々楽しみに♡2024/06/30
piro
45
平将門から西郷隆盛まで、「もののふ」達の争いを、海族vs山族の対立になぞらえて描いた連作短編的な作品。源平、南北朝、戦国、幕末維新と武士が主役だった時代・日本の中世から近代にかけてのオールスターキャストが揃った感。彼らが襷を繋ぐように争い続けて来た歴史の流れを感じさせる興味深い物語でした。それと共に、人は争いをやめる事ができない存在だという事実を突き付けられた様で、複雑な思いも残ります。未だに世界から争いが消えない現実を暗示するかのような印象も受けました。2023/12/09
みねね
41
螺旋を登ったり降りたりするうちに知らない階にたどり着いていたようだ。おかげで歴史小説というジャンルに出会えた。時代考証とか全然よくわからないけれども恐ろしく大変そう。そこにプロジェクトの要素をぶち込んでいくのは並大抵の技量ではできないだろう。この一作が螺旋プロジェクトに説得力を与えたとさえ思える。/ 人と人の争いは、個と個の争いと大いなる流れの一部とを螺旋のように繰り返しているんだろうなと感じた。まだ全作読破前だが、おそらくウタノハテも蒼色以降も、天使も悪魔も以外全て個と個の争いではないか?2024/12/13
なつくさ
39
【螺旋プロジェクト6冊目(中世・近世)】初読みの作家さん。歴史は争いの螺旋。源平から幕末までのもののふ達の争いを描いている。この人物がいなければあの争いは生まれなかった。あの出来事がなければこの時代は生まれなかった。螺旋の争いが今の日本を作ったのだと思うと不思議な気持ちになった。日本が戦争をしていた事実さえもどこか遠くの出来事に感じるのに、もののふ達がいた争いの時代があったなんて夢のように思ってしまう。夏草や兵どもが夢の跡。未来にとっては今も夢のように遠い出来事になるのだろうか。少し寂しく感じてしまうな。2023/01/29
-

- 電子書籍
- 賭けからはじまる最後の初恋 1 コミッ…
-

- 電子書籍
- 虎王の花嫁さん【マイクロ】(11) フ…
-
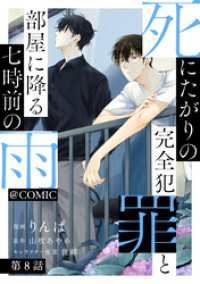
- 電子書籍
- 【単話版】死にたがりの完全犯罪と部屋に…
-
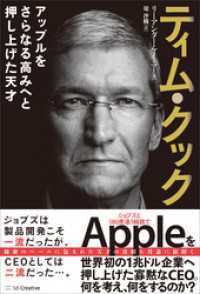
- 電子書籍
- ティム・クックーアップルをさらなる高み…
-

- 電子書籍
- BIOCITY20 自立循環型社会のビ…




