出版社内容情報
軽妙な語り口で市井の人びとの日常をユーモラスに描いた梅崎春生。直木賞を受賞した表題作ほか、「黒い花」「零子」など同賞の候補となった全四篇と、自作について綴った随筆を併せて収める。文庫オリジナル作品集。
〈巻末エッセイ〉野呂邦暢〈解説〉荻原魚雷
■目次
Ⅰ
黒い花/拐帯者/零子/猫と蟻と犬/ボロ家の春秋
Ⅱ
私の小説作法/私の創作体験/わが小説/私の小説作法
〈巻末エッセイ〉名前(野呂邦暢)〈解説〉荻原魚雷
内容説明
軽妙な語り口で市井の人びとの日常をユーモラスに描いた梅崎春生。1955年に直木賞を受賞した表題作ほか、「黒い花」「零子」(全集未収録)など同賞の候補作全四篇と、小説をめぐる随筆を併せて収める。文庫オリジナル作品集。
著者等紹介
梅崎春生[ウメザキハルオ]
1915(大正4)年福岡市生まれ。小説家。東京帝国大学国文科卒業前年の39(昭和14)年に処女作「風宴」を発表。42年立軍に召集されて対馬重砲隊に赴くが病気のため即日帰郷。44年には海軍に召集される。戦争体験をもとに人間心理を追求し戦後派作家の代表的存在となる。『ボロ家の春秋』で直木賞、『砂時計』で新潮社文学賞、『狂い凧』で芸術選奨文部大臣賞、『幻化』で毎日出版文化賞。1965(昭和40)年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
-
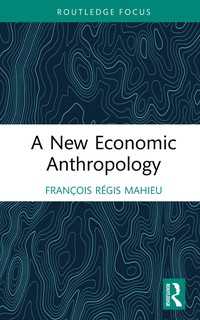
- 洋書電子書籍
-
新たなる経済人類学
A New …
-
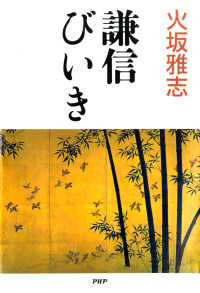
- 電子書籍
- 謙信びいき






