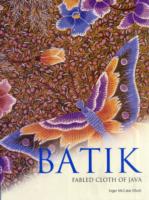出版社内容情報
繁栄か退廃か? 栄達か挫折か? 漱石、鴎外、鏡花、荷風、芥川、谷崎、乱歩、太宰などが描いた珠玉の作品を通して移り変わる東京の多面的な魅力を俯瞰。
長山靖生[ナガヤマヤスオ]
著・文・その他
内容説明
変わりゆく景観は繁栄か退廃か?待ち受ける宿命は栄達か挫折か?めくるめく発展する都市は身上によって見え方も多彩だ。漱石、鴎外、花袋、露伴、鏡花、荷風、芥川、谷崎、寅彦、乱歩、太宰、達治など文豪たちが、様々な時代・地域・立場から描いた珠玉の作品を通して、東京の多面的な魅力を俯瞰する。
目次
三四郎(二)(夏目漱石)
普請中(森鴎外)
明治初年の東京―墨堤と両国(淡島寒月)
東京の発展(田山花袋)
夜の隅田川(幸田露伴)
山の手小景(泉鏡花)
深川の唄(永井荷風)
大川の水(芥川龍之介)
浅草公園(谷崎潤一郎)
銀座アルプス(寺田寅彦)〔ほか〕
著者等紹介
長山靖生[ナガヤマヤスオ]
評論家・歯学博士。1962年、茨城県生まれ。91年に鶴見大学大学院を修了。学生時代から文芸評論家として活動し、1987年、横田順彌、會津信吾らと共に古典SF研究会を創設、初代会長を務める(名誉会長・小松左京)。歯科医の傍ら、近代日本の文化・思想史から文芸評論や現代社会論まで幅広く執筆活動を行っている。『偽史冒険世界』(筑摩書房)で大衆文学研究賞、『日本SF精神史』(河出書房新社)で日本SF大賞、星雲賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
67
芥川と寺田寅彦の作品がセンチメンタル、荷風が当時の世俗をまざまざと描写しているのが印象に残った。昔の東京の風景は、地名以外もはや私の中ではファンタジーと変わらなく映ることに気づく。2018/12/08
HANA
55
明治維新から太平洋戦争まで。漱石、鴎外から太宰まで。文豪たちが描いた東京を、時代順に収録したアンソロジー。個人的に大阪を舞台にした作品はそこに生きる人が描かれるのに対して、東京が土地自体が主人公となっているように思う。本書に収録された作品もその例に漏れず、東京のゲニウス=ロキが感じられるような話ばかり。印象に残った作品は夢野久作の大震災ルポであるが、その他にも月島今昔とか荷風が描く世相の様子等が興味深い。凄まじい勢いで変化する東京ではあるが、時代の変遷を見ると根の部分で変わらない部分があるように思えた。2019/01/16
ヨーイチ
39
帝都物語を読んでいたせいか、帝都って言葉に反応したのかも知れない。某カップ焼そば本と違い、中身は本当の文豪揃いのアンソロジーで中身が濃い。巻頭を飾るのが漱石の「三四郎」鴎外が続き、露伴、鏡花など。帝都物語を引き摺るが如く寅彦も有り、偶然だけど多分この随筆が荒俣の種本だろう。精読すれば、古い順・風景描写が多いため、帝都の変遷と風景描写の違いを味わうことが出来る。編者の長山靖生は初読だが小生が知らなかっただけで、作品リストを見ると中々の品揃え。「文芸好き」な人は読んで損なし。2019/06/21
ワッピー
25
明治から昭和まで、東京をテーマにして描いた作品数多ある中から、夏目漱石の「三四郎」の抜粋に始まり、三好達治「月島わたり」までの25作品を収録。様々に切り取られた時代の窓からのぞき見る東京の風景・人心絵図に漂う2時間でした。特に芥川龍之介「大川の水」の叙情、夢野久作「大東京の残骸に漂う色と匂いと気分」「焼跡細見記」の震災直後の傷跡、吉行エイスケ「享楽百貨店」のいっそ痛快な腐敗ぶりは印象的でした。また、東京小説論となっている編者の後書きは、収録した作家以外にも現代につながる系譜を紹介していて参考になります。 2019/06/30
SIGERU
22
本書を読むと、得心できる。関東大震災の前と後とで、東京がいかに変貌したのかが。 震災前を代表する散文が、漱石『三四郎』、鴎外『普請中』、荷風『深川の唄』。ことに荷風の物は名調子で、江戸情調の残香たゆたう、古き良き東京が偲ばれる。谷崎『浅草公園』は、新派の芝居を低能と決めつけたり、云いたい放題なのが微笑ましい。 震災後の物では、寺田寅彦『銀座アルプス』がいい。幼少の眼に映じた銀座風景を愛情籠めて描く一方、21世紀初めの大震災を既に予見し、備えについて的確な提言をしている。科学者らしい、冷静な筆致が好もしい。2021/11/14