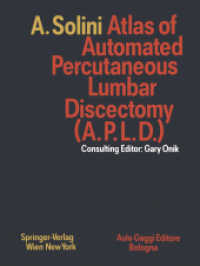出版社内容情報
『山のパンセ』で著名な串田孫一。山に登り、自然に親しむなかで自らと対話し、深い思索を展開した。本書は、1955年(40歳)から、1990年(75歳)にわたって書かれた、山にかんするエッセイのベストセレクション。山に登る人、そして、現実の山登りはしない人も、この本から伝わってくる、山に射す光とその清涼な空気に、魅了されるだろう。
内容説明
山に登り、自然の中に身を置くことで、自らとの対話を続けた思索家の、山エッセイ・ベストセレクション。「何故人は山へ登るのだろう」という問いかけに始まり、山行きの持ち物から記憶に残る思い出の山々、詩篇まで、四十六篇を収録。
目次
1 小前奏曲
2 身支度
3 山想
4 山の博物誌
5 心の山
6 詩篇
著者等紹介
串田孫一[クシダマゴイチ]
1915年、東京生まれ。東京帝国大学でフランス哲学を専攻。中学時代から登山を始め、大学在学中から『山と溪谷』などの山岳雑誌に執筆する。上智大学、東京外国語大学などで講義を持つ傍ら、雑誌や新聞への執筆、講演活動など幅広く行い、55年に『若き日の山』を刊行以降は、山に関する文章を書く機会が増える。主な著書に『山のパンセ』があり、小説、哲学書、画集、詩集など、著作は多岐にわたる。2005年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gonta19
107
2018/2/10 メトロ書店御影クラッセ店にて購入。 2020/11/5〜11/6 思索家としても著名な串田氏の山に関するエッセイなど。昔の山の様子が分かって興味深かった。2020/11/06
Shoji
61
自然を愛し、山を愛する作者のエッセイ。名だたる日本の山の感想、道具にまつわる話、山をどうスケッチするか、山の歩き方、観光開発に関する警鐘、四季折々の山の姿、などなど、豊かな大自然に逆うことなく自然体で山に接している作者の姿が浮かびました。いい文章が綴られていました。2018/04/04
HANA
59
山に関する随想集。「我々は何故山に登るのか」という問いから始まり、愛着のある道具類の数々、山道を行く途中での風景やそれを彩る季節や動植物、信州や関東、北海道の思い出の山々等を語って止む事がない。それが独特の透明感のある文体で記されているので、読みながら暖かくなりつつある日差しの中を歩く春の山道や、木々を揺らし落ち葉を巻き上げる秋風の中を歩く心地が思い出さされる。いいなあ、やはりこういう本を読むと山に行きたくてたまらなくなるなあ。読みながら今までの山行と登りたい山への渇望が沸き上がる、いい一冊であった。2018/03/24
くみ
22
【雪の日に】小島聖さんのエッセイで知った串田さん。登山家の方なんだろうと思ってたら本業はフランス哲学。そして想像以上の登山家でした。雪山はもちろん、必要があれば野宿も、また夜通しの峠越えも辞さない。その紡がれる言葉は静けさと威厳があり父性を感じました。同時にとても詩的なロマンチシズムも感じます。呼んでいるととても安らぐ。後半は実際に山に登る方のためのエッセイが多く愛好家の方はより楽しめるかも。最後が詩でしめくくられてるのも余韻が残ります。2019/02/02
あきあかね
20
気品ある詩情に満ち、かつ思索的で、著者の山への愛情が感じられる一冊。 深田久弥の名著『日本百名山』が、具体の山を取り上げ、山が詠まれた和歌や歴史などを織り交ぜるのに対し、本書で現れる山々の多くは、具体の名前は示されない。 それによって、読み手は自身がこれまでに登った、心の山の想い出を自由に投影できる。夏山の草いきれと壮麗な夕映え、晩秋の山で出会した清冽な泉、冴え冴えとした月の輝きと雪の匂い、白樺の樹皮にそっと羽を休める春の蝶ー。見本帳のようにあふれる、四季折々の山の魅力によって、想像が広がってゆく。⇒2019/05/18
-

- 和書
- ねこのいえで