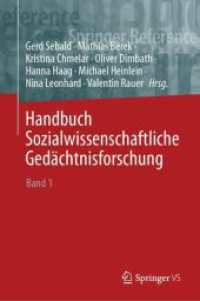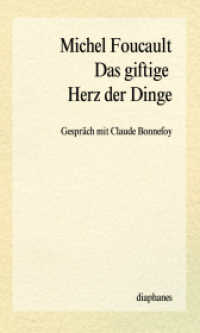内容説明
弥生時代、農耕社会への移行とともに、日本列島中央部でも本格的な集団間闘争が広がっていった。武器によって傷つけられた人骨、副葬された武器や武具、そして巨大古墳…。膨大な発掘資料をもとに列島の人びとの戦いの様相を探り、さらに戦争発動のメカニズムと日本の軍事的特質をも明らかにする。
目次
第1章 戦争の根源をさぐる
第2章 戦士の誕生―弥生時代の戦い
第3章 英雄たちの時代―弥生から古墳へ
第4章 倭軍の誕生―「経済戦争」としての対外戦争
第5章 英雄から貴族へ―古代国家の形成
第6章 国の形、武力の形―古代から中世へ
第7章 戦争はなくせるか―考古・歴史学からの提言
著者等紹介
松木武彦[マツギタケヒコ]
1961年、愛媛県生まれ。大阪大学大学院文学研究科博士課程修了。岡山大学文学部教授を経て、国立歴史民俗博物館考古研究系教授。専攻は考古学。文学博士(大阪大学)。2008年、『列島創世記旧石器・縄文・弥生・古墳時代』(全集日本の歴史1)でサントリー学芸賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
京都と医療と人権の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
11
主に考古学の知見から、日本古代の戦争のあり方を探る。日本の古代はアジア的な専制国家よりは、ポリスが林立し、かつそれにも関わらず人々が生活様式などの面で一体性を持っていた古代ギリシアに似ているという話や、武器の実用性・機能性よりは装飾性を増す方向で発達した期間が長く、騎馬戦対のような新しい軍事技術の導入には消極的な態度を取ったようで、そこから日本人の軍事思想に対する保守性が読み取れるのではないかという話が面白い。2018/06/13
CTC
9
17年9月中公文庫新刊。初出01年講談社メチエ。著者は国立歴史民俗博物館教授。考古学の見地から“集団間闘争”を時系列で考察し、類型を導き、教訓を導こうとする。 日本列島は「おもに島国という地理的条件によって」、古代国家は“軍事的征服”によってではなく地域勢力の系列化により形成され、さらにその後も外敵脅威がなかった。この事が武器や戦術の「保守的精神性」に繋がり、先の大戦の結果にすら結びついている、と。まさしく大岡昇平さんが『レイテ戦記』で記した、兵士たちは「日本の歴史自身と戦っていたのである」、ですなぁ。2018/03/23
月をみるもの
8
歴博に松木さんの講演会を聞きに行ったついでに、ショップで購入。教科書的には「中央集権的な律令国家の崩壊→地方の武士の台頭」と習うわけだが、実際は古墳時代から武力の中心は地方にあり、律令が整備されたあとも変わってない、、、、というのが印象的であった。そういう意味で日本が本当に外敵の脅威にさらされ、武力統一による中央集権国家となったのは戊辰戦争が初めてだったのかもしれない。。2018/04/15
坂津
1
先史時代から近世まで、その中でも主に弥生時代から飛鳥時代にかけての武器の変遷を辿ることで、倭(日本)の戦いの在り方を描き出す著書。渡来人の日本列島への流入や倭軍の朝鮮半島への侵入を背景として、武器の改良や馬の導入、山城・水城の整備などの影響は受けつつも、四方を海に囲まれ外敵との接触に乏しいため、実用的な武器・戦術への革新がなされにくい日本の軍事面での特殊性が浮かび上がる。白村江の戦いの後に列島各地に築かれた山城・水城の非実用性、兵力の動員方法の違いで見る壬申の乱の勝敗など、意外かつ興味深い指摘が多かった。2020/09/25
iwasabi47
1
著者の専門の考古学からみる戦争。古墳時代槍よりも太刀が発達したのは歩兵主体で騎兵が発達しなかったのは言われてみればそうだなと。歩兵主体から騎兵主体にどう移ったのかが私的には気になる。2018/06/21