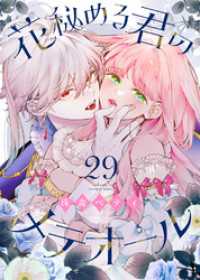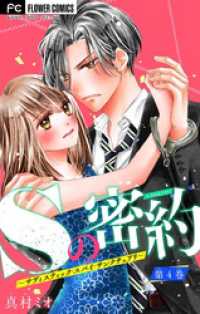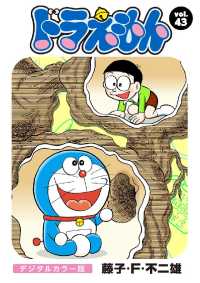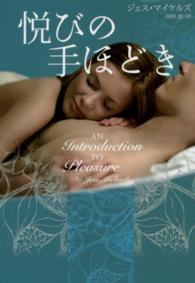出版社内容情報
『万葉集』から『サラダ記念日』まで。言語学者と小説家の双璧が、文学史上の名作を俎上に載せ、それぞれの専門から存分に語り合う。日本人の場所感覚から、「てにをは」の重要性に至るまで、徹底的に追究し、日本語の本質を探る知的興奮に満ちた対談集。 〈解説〉大岡信 金田一秀穂
内容説明
『万葉集』から『サラダ記念日』まで。言語学者と小説家の双璧が、文学史上の名作を俎上に載せ、それぞれの専門から存分に語り合う。日本人の場所感覚から、「てにをは」の重要性に至るまで、徹底的に追究し、日本語の本質を探る知的興奮に満ちた対談集。
目次
鴨子と鳧子のことから話ははじまる
感動詞アイウエオ
蚊帳を調べてみよう
「ぞける」の底にあるもの
「か」と「や」と「なむ」
已然形とは何か
「こそ」の移り変り
主格の助詞はなかった
鱧の味を分析する
岸に寄る波よるさへや
場所感覚の強い日本人
現象の中に通則を見る
古代の助詞と接頭辞の「い」
愛着と執着の「を」
「ず」の活用はzとn
『万葉集』の「らむ」から俳諧の「らん」まで
「ぞ」が「が」になるまで
著者等紹介
大野晋[オオノススム]
1919年、東京生まれ。東京大学文学部国文学科卒業。専攻は国語学。恩師橋本進吉博士の上代特殊仮名遣の研究を発展させた「上代仮名遣の研究」がある。学習院大学名誉教授。2008年、死去
丸谷才一[マルヤサイイチ]
1925年、山形県鶴岡市生まれ。東京大学文学部英文科卒業。小説、評論、翻訳、エッセイと幅広い文筆活動を展開。2012年、死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Haruka Fukuhara
りやう
猿田康二
原玉幸子
はちめ