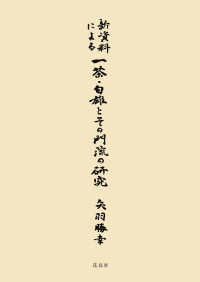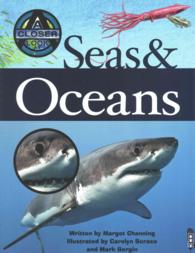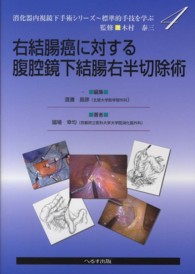内容説明
一九一六年一月に発表され、民本主義を唱道した「憲政の本義を説いて其有終の美を済すの途を論ず」は大きな反響を巻き起こしたが、「有終の美」が遠いことは現在の私たちがよく知ることでもある。有権者の覚醒こそがデモクラシーの根本だと説き続けた吉野の真骨頂を伝える六篇を収録。
目次
憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず
民本主義・社会主義・過激主義
帷幄上奏論
護憲運動批判
現代政治上の一重要原則―民主主義は何故わるいか
憲法と憲政の矛盾
著者等紹介
吉野作造[ヨシノサクゾウ]
1878(明治11)年宮城県に生まれる。東京帝国大学法科大学政治学科卒業後、大学院に進む。1906年、袁世凱長男の家庭教師として中国・天津へ赴く。10年、政治史・政治学研究のため欧米に留学、帰国後、東京帝国大学教授となる。16(大正5)年1月、『中央公論』に「憲政の本義を説いて其有終の義を済すの途を論ず」を発表、以後二〇年近くの間、『中央公論』の看板執筆者として活躍する。24年、東京帝国大学教授を辞職し、朝日新聞社に入社するも三ヵ月で退社を余儀なくされる。同年、明治文化研究会を組織。33(昭和8)年、結核のため没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
yo
10
吉野作造の民本主義という概念になんとなく興味があったので。主権が本質的に人民にあるとする哲学的民主主義は「危険思想」だとするのはなかなか面白い。これによれば戦後日本は危険思想に侵された国だということになる笑。この貫徹のために必要なものとして、一番大事なのは人民や議員、政府のいずれにも求められる「道徳」であることは、論理的に当然だと思う一方で制度設計の限界を認めざるを得ない苦しみもある。吉野はその道徳のための政治教育はもはや充分であるとしていたが、今の選挙行動やニュースや見てるとほんとに充分かは甚だ疑問。2016/08/06
ア
6
「吉野作造−民本主義」は知っているけど、恥ずかしながら読んだことがなかった。1910年代から20年代までの吉野の論稿が収められた本書だが、思いの外読みやすく、論点もわかりやすい。民衆の政治参加や憲政の立憲的な運用を説き、右派の官僚主義や左派の民衆独裁を批判する。また解説で苅部直氏が、民本主義は吉野が便宜上用いたもので、その前に上杉慎吉が使用していたと指摘しており驚いた(つまり、「民主主義に満たない民本主義という不十分なデモクラシー観を説いた吉野」という見方は不適当)。2023/07/09
山像
4
「憲政の本義を説いてその有終の美を済すの途を論ず」はデモクラシーが機能・発展していく上での基本的な前提条件について説いた論文、「帷幄上奏論」は一見明白に憲法の条文に違反している慣習をどのように扱うかというかなり技術的な話、「護憲運動批判」は“憲政の精神にそぐわず正当性のないように見える政権(清浦内閣)に対して有権者は如何なる理路でいかなる裁定を下すべきなのか”という大変実際的な話, etc. まあものの見事に「日本は100年前から大体同じような問題に直面してきたのか……」と思わされるような構成になっている2016/07/17
熱東風(あちこち)
4
読んでいるうちに、吉野が現行憲法下で生きていたら現在の政治状況をどう評価するのか見てみたい欲求に駆られた。主権が天皇から国民に移り、『民本主義』と『民主主義』の違いを強調する必要がなくなった現代の政治を。/以下の論旨は現在に照らし合わせてみると、日本の政治は成長していないという気がする。『選挙権が拡大すれば腐敗が減少する』『詰まらない人間は議員になる資格がない』/本書を読書中に参政権年齢18歳引き下げや、国民投票による英国のEU脱退などが話題になっていたことが、偶然であるが何とも妙な感覚に襲われた。2016/06/30
zenigatasho
3
吉野作造による憲政、民本主義、軍閥批判、ポピュリズム批判論集。 一般的には、民本主義を、民主主義の下位互換として、天皇主権を乗り越えられない、帝国日本の限界としている。しかし、吉野の民本主義は、国民の意向を踏まえて政治をするという、民主主義の下位互換であるどころか、根底にある基礎を述べたものである。 本書を読んで、無知なる故の大正デモクラシー、民本主義への低評価を、改めさせられた。 「憲政の本義を説いて」は今年で、100周年目らしく、そんな年に吉野作造の考えを少しでも知ることができて良かった。2016/07/29
-
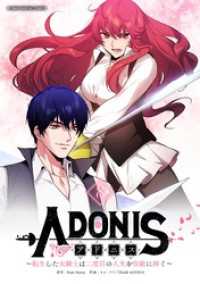
- 電子書籍
- アドニス ~転生した女騎士は二度目の人…
-
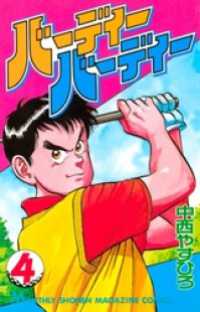
- 電子書籍
- バーディーバーディー(4)