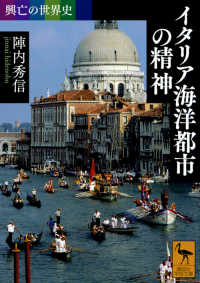出版社内容情報
大江戸庶民の大半が居住していたのが長屋である。長屋生活に仕きたりや作法など、さまざまな仕組みがあった。その暮らしぶりを活写した秀逸な一冊。
内容説明
江戸庶民のほとんどが住んでいた長屋。大家は親も同然といわれ、入居希望者の人柄の見極めに始まり、夫婦喧嘩の仲裁冠婚葬祭の仕切りまで、店子たちの世話を焼いていた。一方、店子は年に一度の井戸浚いや、煤払いなど、季節の行事の取り決めを守りつつ貧しくも長閑に暮らしていた。そんな江戸っ子の日常を小咄、落語に絡めて活写する一冊。
目次
1 長屋の朝・昼・晩―粋と情の世界に遊ぶ(江戸の市政;表長屋と裏長屋;時のはなし;江戸ッ子の朝 ほか)
2 路地を行き交う行商人たち―ぬくもりにあふれた生活空間(魚売り;野菜売り;惣菜用食品売り;季節の行事用品の行商 ほか)
3 ささやかな楽しみ―“ハレ”の時間の過ごし方(食べ物店;街頭芸人;行楽;信仰と娯楽)
著者等紹介
興津要[オキツカナメ]
1924年栃木県生まれ。49年早稲田大学文学部国文学科卒。51年まで大学院に在籍、教育学部助手。56年同専任講師、59年助教授、68年早稲田大学教育学部国語国文学科教授、94年定年退任、名誉教授。専門は近世後期の滑稽本と明治期の落語、戯作、ジャーナリズム。99年に死去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。

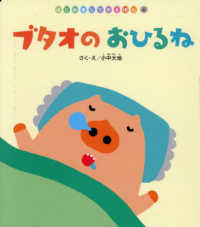

![[図解]病気にならない「白湯」健康法 - あらゆる不調がスッキリ改善!](../images/goods/ar2/web/imgdata2/45698/4569842291.jpg)