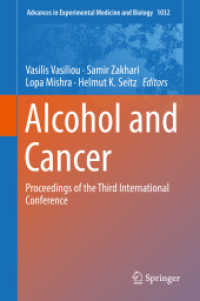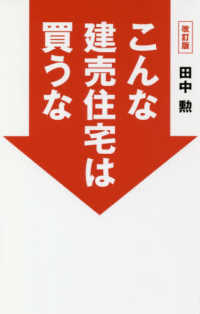出版社内容情報
日本の文化は水の文化と言っても過言ではない。先人たちが各地に残した歴史の痕跡を訪ね歩き、そこに息づく知恵と思想を鮮やかに紹介。水を通して日本の未来を考えた、心打つルポルタージュ。
内容説明
日本の文化は水の文化。そして、日本は「木を植える文化」の国である。米、酒、鮭、杉といった身近なものにも、人が自然に働きかけてきた苦心の歴史がある。先人たちが各地に残した歴史の跡を訪ね、そこに息づく知恵と思想を紹介する。自然環境が激変してゆく時期に、水を通して日本の未来を考えた心打つルポルタージュ。姉妹編に『水の文化史』。
目次
お堀の水はどこから
信濃川の本マス
遠賀川の鮭神社
森林は海のサカナを養う
水の文化・チューリップ
赤城山のツツジ
阿蘇の水を作る話
海水から川水を汲み上げる話
人工河川
名水と酒とスギ
九頭竜川の舟橋
植林のはじまり
木を伐るということのすばらしい意味
富士山が割れる
海抜けの話―五十里湖物語
琵琶湖の大運河計画
アジアのダムと森林
著者等紹介
富山和子[トミヤマカズコ]
1933年、群馬県に生まれる。早稲田大学文学部卒業。立正大学名誉教授。自然環境保全審議会委員、中央公害対策審議会委員、林政審議会委員、名水百選選定委員、国際コメ年日本委員会副会長等を歴任。「富山和子がつくる日本の米カレンダー」を制作(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
45
日本各地の水と人、森と人との関係を考察した一冊。読んでいると日本人が如何に水と付き合い、時には氾濫を起こされることもあるとしても、それを利用して来たかが興味深い。最も興味深かったのは琵琶湖と日本海を運河で繋ぐ計画。平清盛以来何度となく企てられたものの、様々な要因により頓挫したプロジェクトだが、陸運が中心の現在だとこれ以上計画される事はないのだろうな。個人的には琵琶湖が小さくならないで良かったような気もするけど、これも現在からみたエゴかなあ。先の『水の文化史』同様、自然と日本人の関係を描いた名著であった。2014/10/18
リョウ
3
昭和末に書かれた日本の水にかかわるエッセイ集。先人達が森に手を入れて豊かな水が得られるように維持されてきた国土もこの40年ほどの間に随分と様変わりをしていて、森の保水力は随分と落ちてしまっているように思う。果たしてこの先も今までのような豊かな水が維持できるのかは随分と心配になる。2024/12/06
日向夏(泉)
3
日本を中心にアジアまで広く、水と人間の関わり合いを取り上げている。現代日本の私たちが当たり前に享受している飲料水や、治水の恩恵は、先人のたゆまぬ努力のうえにあることを痛感する。各地の具体的な水利を知ることで、当時の人々が肉体をもって書物の中から立ち上がってくるようである。2016/08/18
veryhot
1
日本の北海道から九州まで、森と水との接し方が色々書いてある。興味深い話題が詰め込まれていて、ネタ探しにはとても良い。…のだが、根拠や詳しい説明はあまり無く、話題があっちこっちに飛ぶ物知りおばちゃんのお話、という感じ。細かいことや疑問に感じたことは自分で調べてみると面白い。2021/02/06
タマサブロウ
0
お堀の水ってどこから来てるんだろう? とか土木関係の話が、わりと印象に残った。重盛様がムリって言ったんだから、あきらめようよ!ほらまた1億もムダにしてーとか。2013/09/26