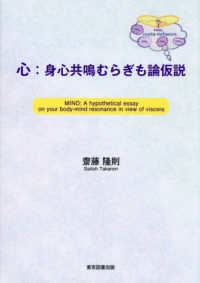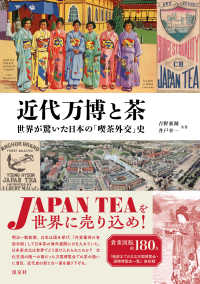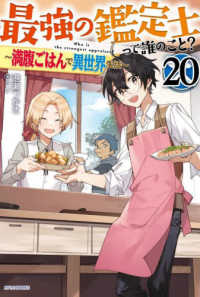内容説明
「偉大な明治」が去り、日露戦後の帝国日本は模索していた。しかし、大正期日本は「大正ロマン」という陳腐な表現に示されるような、明治と昭和の間に咲いたひ弱な花ではなかった。大正デモクラシーの出発点となる一方、欧米列強の狭間で新たなナショナリズムが胎動する激動の時代を描く。
目次
プロローグ 日露戦後という時代
1 帝国日本の模索
2 第一次世界大戦と日本
3 戦後世界秩序と帝国日本のナショナリティ
4 「ワシントン体制」と日本
5 社会の発見
エピローグ 発見されたのは何か?
著者等紹介
有馬学[アリママナブ]
1945年(昭和20)北京生まれ。東京大学文学部卒業。東京大学大学院人文科学研究科満期退学。九州大学名誉教授、福岡市総合博物館長。日本近代史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroshi
10
日露戦争終了から普通選挙実施までの本。日露戦争と第一次世界大戦の戦後を扱う。勝った戦争の戦後だ。日露戦争で朝鮮と満州利権を獲得した。朝鮮は皇帝の譲与により併合される。満蒙問題は遼東半島租借地と鉄道だけだが、それが欲望により拡大する。更に辛亥革命で複雑化する。また日本人は世界の日本の政治や社会は世界の大勢に対応すべしと思考しだすのだ。初めの約10年は官僚閥の代表の桂太郎と政友会総裁の西園寺公望が交互に政権を担当した。政友会が利権政治で衆議院の第1党であり続け、原敬が官僚閥との取引で政権政党の立場を維持した。2025/04/03
ふみあき
2
第一次大戦後、米国のウィルソン大統領が、旧来の植民地支配(領土的併合)に代えて「委任統治」方式を提唱したように、欧米列強は露骨な帝国主義的主張を控えざるをえなくなる。また日本は1919年のパリ講和会議において、国益追求の際のエクスキューズに過ぎないとしても、人種の平等を世界に高唱した。偽善的ではあるが、歴史の進歩とは、建前の存在による本音の掣肘によって、少しずつ実現されるものなのかもしれない。2020/05/22