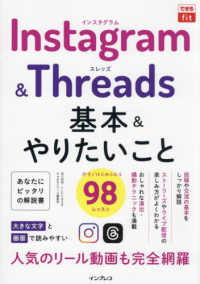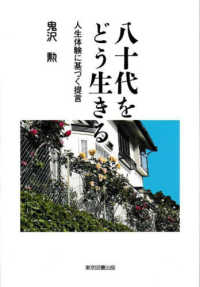内容説明
人はなぜ本を読むのか。時を忘れて読みふけった思い出や、長大な作品を意地になって読み通した経験は誰にでもあるだろう。まったく歯が立たない本、価値観や存在を揺さぶられるような危険な書物も、読書体験には欠かせない。著者が成長していく時代、書物は、まばゆい、あるいは妖しい光を放っていた。書物への感謝に満ちた、赤裸な読書体験記。
目次
序章 そこに本があるから本を読む
第1章 時を忘れて読みふける
第2章 意地でも最後まで読み通す
第3章 思春期の書物と出会う
第4章 わからない本と格闘する
第5章 危険な書物に誘惑される
第6章 言葉の美に魅了される
終章 今日もまた本を開く
著者等紹介
石井洋二郎[イシイヨウジロウ]
1951年、東京生まれ。82年、京都大学教養学部助教授。87年、東京大学教養学部助教授。94年、同大学教授。91年、ブルデュー『ディスタンクシオン』の翻訳により渋沢・クローデル賞を受賞。2001年、『ロートレアモン全集』で日本翻訳出版文化賞・日仏翻訳文学賞を受賞。09年『ロートレアモン 越境と創造』で芸術選奨文部科学大臣賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金城 雅大(きんじょう まさひろ)
30
共感、納得ができる読書論が多く書いてあり良い本だと思う。 気になるところに線を引きながら読んだので、折に触れ読み返したい。2020/02/29
SOHSA
16
『告白的読書論』この不思議なタイトルに惹かれて行き付けの書店でふと手に取った。あっという間に引き込まれた。自分自身と重なり合う部分の何と多いことか。共感できることの喜び、楽しさ。きのおけない旧友とばったり再会したような感激があった。そうそう、そうだよなと本に語り掛けるようにひとり頷く自分がいた。読書って本当に素晴らしい。2013/02/20
harass
14
フランス文学者が自分の中高学生時代の読書遍歴を中心に読書についてを語る。語り口が適度に軽く題名の物々しさとは逆に読みやすい。ある程度の読書家であれば当然とうなずけることが多く、感じてはいたが言葉にできずにいた部分をきちんと言葉にしていて唸らせられる。「自分を崩す読書」などの読書の様々な効用には非常に共感できた。小説や思想哲学の本だけではなく、戯曲や詩を取り上げている。詩についての部分が、短いが良質な鑑賞入門になっている。個人的に気になっていた詩人ばかりでてくる変な偶然に驚いた。ぜひ読書家に一読を願う良書。2013/05/22
内緒です
13
こんだけ読書に心酔できる人になりたい。2013/05/19
swshght
12
最近、読書論が盛んだ。『もうすぐ絶滅する~』は別格だったとしても、この手のものは「電子書籍時代の読書」と「物質としての本への愛着」を論じたものばかりで、いよいよ飽きてしまった。本書はどうか。立場は明快だ。「『そこに本がある』かぎり、人は本を読む」。まるで登山家のような潔さだ。著者は自身の読書体験を赤裸に告白しながら、小説、哲学書、詩集、妖しい危険な書物(!)など、具体的な作品を次々と挙げていく。小難しい話は抜きに、ただ「読書の楽しさ」の一点に焦点をしぼり、心躍る読書論を展開する。さて、今日も本を開こうか。2013/05/17