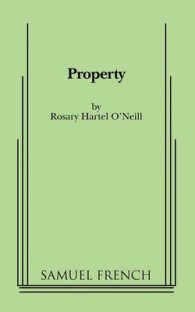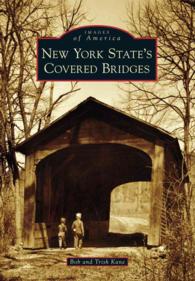内容説明
西欧文明との出会いは、日本の佇まいに何をもたらしたのか。それは、「場所」として存在した日本古来の建築物が「空間」と出会うことによって、都市が近代へと脱皮する出発点だった。文明開化、大震災、戦災、高度経済成長―変容する都市の風貌から、日本人のアイデンティティの軌跡を検証する。
目次
第1部 開国と首都(開国と開港;江戸から東京へ;土地の持ち方・使い方―東京(近代における三都論)
都市計画の出発)
第2部 近代における京・大阪(琵琶湖疎水計画とその展開―京都(近代における三都論2)
「阪神間」という土地―大阪(近代における三都論3))
第3部 新しい生活の出現(震災復興計画;郊外の成立)
第4部 戦後の展開(戦後の運命;都市は豊かになるか)
著者等紹介
鈴木博之[スズキヒロユキ]
1945年、東京都生まれ。東京大学大学院工学系研究科建築学専攻課程修了。東京大学教授、早稲田大学客員教授を経て、2009年より青山学院大学教授。2010年より博物館明治村館長併任。1985年、『建築の七つの力』(鹿島出版会)で芸術選奨文部大臣新人賞、90年に『東京の「地霊」』(文藝春秋)でサントリー学芸賞、96年に日本建築学会賞、2005年に紫綬褒章を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Hiroshi
8
文明開化・大震災・戦災・高度成長と都市は変容していった。それを見ていく本。観光旅行は都市と建築の見物だという。都市の精神はヨーロッパでは廃墟であり、日本は名残の風情だという。時間の体験だという。日本の都市は平屋からなる。都市は建物と公園のモザイクからなる。江戸の町は6割が武家地であり、1割が寺社地で、3割が町人地であった。武家地と寺社地は拝領地であり、町人地は沽券地(売買可能な地)だった。明治になると拝領地が政府の所有となる。武家地に武士はいない。武家地は貸し出され、空き地は桑茶政策が取られて畑となった。2025/05/09
chang_ume
3
評価の難しい一冊です。日本都市の「近代化」について、ひとつは公共政策の面から叙述。たとえば武家地や寺社地といった近世的な場が変容する画期として、挙げられた「桑茶令」は特記事項でしょう。もうひとつは土地所有の面から都市近代化の読み解き。「地主」の分析は土地の近代的再編成を活写しました。誰がどのように都市を所有したのか。一方であり得べき参照軸として、西欧モデルの絶対化には閉口も。文化受容の視点が決定的に乏しい。伝播モデルがあまりに中心からの遠近法に依拠しています。伝播・受容とは規範の忠実なコピーではないはず。2017/02/10
豆乳みたらし
1
地主クラスの所有者から見る近代史が面白かった。土地に起こった歴史だけでなく、誰がどういう意図で所有したかによって翻弄されもする土地の歴史があるということを教えてくれました。古き良き歴史が無くなる無常の感は近代化が起こった瞬間、現代人からすると昔に当たる明治時代から感じられていたことを垣間見るようでした。2015/02/08