内容説明
夜ごと人間の血を舐る一本足の美女、蝦蟇に祈祷をするうら若き妻、井戸の底にひそむ美少年、そして夜店で買った目隠しされた猿の面をめぐる怪異―。ひとところに集められた男女が披露する百物語形式の怪談十二篇に、附録として単行本未収載の短篇二篇を添える。
著者等紹介
岡本綺堂[オカモトキドウ]
1872年(明治5)東京生まれ。本名は敬二。元御家人で英国公使館書記の息子として育ち、「東京日日新聞」の見習記者となる。その後さまざまな新聞の劇評を書き、戯曲を執筆。大正時代に入り劇作と著作に専念するようになり、名実ともに新歌舞伎の作者として認められるようになる。1939年(昭和14)逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
syaori
67
ある早春の雪の晩、青蛙堂に集まった人々が「珍らしいお話」を語るという趣向の短編集。江戸から大正にかけてを舞台とした物語が並びます。猿の面の眼は暗闇に光り、訪ねてきた友人が服装はそのままにあくる日に別人の死体となって発見され、井戸の底には美貌の公達が現れるなど、物語られるのは素敵に奇妙で蠱惑的なお話ばかり。怪異の因果や由縁などは明らかにならない場合が多いのですが、それがまた味わい深い余韻を残すようで、時に深い闇に、時に蝋燭に照らされたほのぐらい夜のしじまに耳を澄ますように、上品で魅惑的な怪談を愉しみました。2022/02/16
mii22.
58
百物語形式で12名の語り手により披露される怪談。最初のひとりをのぞいて、二人目からは名を伏せて「第二の男は語る。」と始まるところが趣があって雰囲気を盛り上げる。一篇一篇読み始めると物語の世界にぐっと引き込まれていく魅力的な語り口は古さを感じさせず適度な品のよさと怖さがあり大変好みだった。2022/08/28
澤水月
32
三本脚のガマへの妖しい信仰が悲劇生む「青蛙神」や「窯変」など本物の志怪もの読んでいるよう(著者自身日本に中国口語怪奇小説を紹介した泰斗)。日露戦時、満州の日本人と中国民の関係は良好だったのも初めて知る。コレラ禍にまつわる哀話で「ご新造」と呼ばれる囲われた女性という存在そのものには差別視がないのも興味深い(綺堂も同時代人の鏡花も芸者を落籍し妻にしているからか)。新しく知る風俗・言葉が全て新鮮で非常に上品、しかし実はえぐい。幼女神隠し話は人間の業と当時の身分制の悲劇。ひたすら近くて遠い時代に酩酊できる2018/09/06
HANA
30
何度目かわからない再読。凡百の怪談がけばけばしいネオンサインなら、これは漆塗りといった趣を持っていると思う。派手な光こそないけれど、その沈んだ輝きは見る人が見るとたまらない。どの作品を読んでも外れはないが、個人的に気に入ったのは、不思議な女によって侍の運命が転落していく「一本足の女」と面の描写が何とも気味の悪い「猿の眼」。他にも心霊譚あり中国の志怪風の物あり民話風ありと、常に読者を引き込んで飽きさせることがない。怪談に興味がある人も食わず嫌いの人も、この一冊だけは読んで損はないと言える、そんな一冊。2012/10/26
ちくわん
23
1926年の本を底本としたKindle版で読了。青蛙人(せいあじん)、利根の渡、兄妹の魂、猿の目、蛇精、清水の井、窯変、蟹、一本足の女、黄いろい紙、笛塚、龍馬の池の12話。このうち10話は1924年(大正13年)12月~1925年9月に「苦楽」に掲載された。「一本足の女」は怖い。2023/01/15
-

- 電子書籍
- 天狗奇譚
-
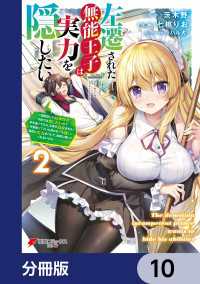
- 電子書籍
- 左遷された無能王子は実力を隠したい【分…
-
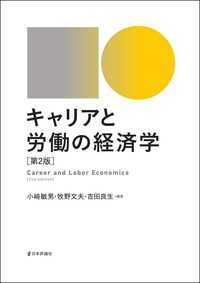
- 電子書籍
- キャリアと労働の経済学(第2版)
-
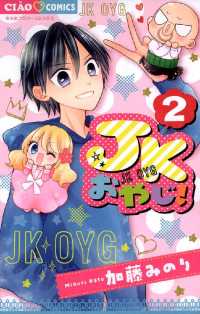
- 電子書籍
- JKおやじ!(2) ちゃおコミックス
-
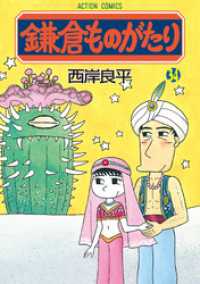
- 電子書籍
- 鎌倉ものがたり 34巻 アクションコミ…




