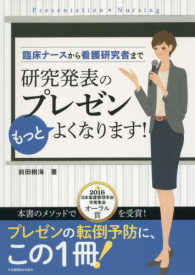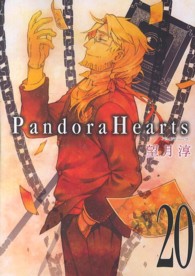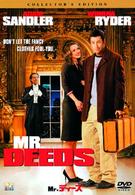内容説明
ペリー来航に始まる幕末の波瀾。欧米各国の圧迫と国家の危機を、人々は英知と戦略で切り抜ける。日本がアジアで唯一近代化に成功したのはなぜか。日本人とは何かを近代国家誕生の過程から描く。
目次
1 ペリー来航(黒船と「白旗」;砲艦外交と阿部正弘;アメリカ、「開国と通商」を要求する;開国策にむかって)
2 開国(ロシア艦隊の来航;日米和親条約の締結;洋式海軍の建設;西洋への対抗意識)
3 攘夷と尊王(水戸学の国体論;開国のほんとうの意味;「日米修好通商条約」とハリス;安政の大獄)
4 国民国家への道のり(咸臨丸、アメリカへ;桜田門外の変;文久三年のクーデター;国民義勇軍としての奇兵隊)
5 戊辰の戦乱(禁門の変;薩長同盟の成立;大政奉還;戊辰戦争と「万国公法」;隠岐島と排仏毀釈運動)
6 維れ新なり(遷都;五箇条の御誓文;第二革命としての廃藩置県;米欧回覧使節団―文明開化への道)
著者等紹介
松本健一[マツモトケンイチ]
1946年(昭和21)群馬県生まれ。東京大学経済学部卒業。法政大学大学院在学中に『若き北一輝』を発表。以後、日本の思想・政治・文学についての評論活動を展開。現在、麗澤大学教授。主な著書に、『近代アジア精神史の試み』(岩波現代文庫、アジア太平洋賞受賞)、『評伝北一輝』(全五巻、岩波書店、毎日出版文化賞、司馬遼太郎賞受賞)ほか多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
10
ペリー来航~廃藩置県・岩倉使節団まで。幕府・薩摩・長州・水戸・会津、どれかに偏ることなく書かれている。41頁。ペリー艦隊は、徳川斉昭が予想していたように、この帰途、「戦争がない」琉球に強引に貯炭所(基地)を設置してしまっている。また、アメリカはこの45年後(1898年)に、やはり軍事的な備えがなかったハワイを併合している。嘉永6年の時点で、アメリカが実際には日本に戦争を仕掛けず、併合もしなかったのは、日本がまがりなりにも統一的な政体をととのえ、その指令のもとに軍事的な備えをもっていたからにほかならない。2018/02/24
Hiroshi
7
ペリー来航から米欧回覧使節団までの本。勝海舟は横井小楠の思想と西郷隆盛の政治を非常に評価しており、その2つが結びつくと革命が生まれると。この2人を結び付けたのが坂本龍馬であり、薩長同盟や大政奉還だけではない。ペリーは万国公法の白旗の意味を告げる。戦争も辞さずだ。ペリーの外交は砲艦外交だった。水戸学は儒学的な名分論だ。ここから日本における名分論として尊皇思想を打ち出した。これに時務論の性格を帯びて幕藩体制下の尊王攘夷論としたのが会沢正志斎の『新論』だ。志士のバイブル。更に尊皇倒幕論にしたのが吉田松陰なのだ。2025/03/21
ふぁきべ
6
知ってるようで知らないペリー来航、日本の開国、そして倒幕へ至るまでの歴史が描かれる。非常に読みやすく、流れもとてもつかみやすかった。唯一の難点は時折話が前後して、そして日時記載がないことがあったりして前後の流れがつかみづらいことがあることか。特に禁門の変の話が二度出てきたときは結構混乱した。それ以外はとてもよかったと思う。 まぁそれにしても日本は外からの強制がない限り自分で自分のルールを大きく変えられない国であるということは昔から変わってないんだなあ、と改めて思った。2017/05/03
ドクターK(仮)
4
幕末から明治維新までの日本の歩みを辿る本書であるが、ただ史実を羅列するだけではなく、随所に著者の解釈・解説が加えられており興味深かった。特に、ペリーによる開国の要求の背景には、日本の開国はアメリカの利益のみならず、日本の進歩、ひいては文明社会全体の発展につながるという使命感があったという指摘には思わず膝を打った。今日のネオコンの思想にも通じるであろう、お節介でいささか傲慢な「アメリカ的使命感」である。また、戊辰戦争においてすでに国際法に則った(うまく利用した?)戦法が用いられていたというのにも驚いた。2018/02/11
広瀬研究会
3
松本健一さんって歴史家というより評論家・思想家なんだと思うけど、それだけに独自の切り口が随所に見られて面白かった。特に川路聖謨や島津斉彬、佐久間象山など、立場は違えど開明派と呼ばれる人たちが、列強と向かい合う姿がすがすがしかった。それと西郷どんはやっぱり奥が深いな。同時代の人々に対する人気や影響力を考えると、ただの有能な政治家・軍人にとどまらない何かがあったんだろうと思えて、もっと詳しく知りたくなりました。2015/06/14



![共通テスト総合問題集 英語[リーディング] 〈2026〉 河合塾SERIES](../images/goods/ar2/web/imgdata2/47772/4777229513.jpg)