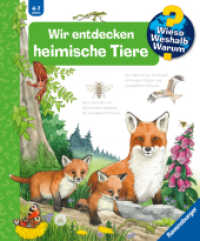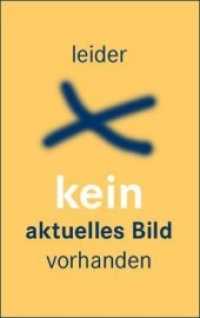内容説明
作ることにあこがれ、二二歳ではじめて粘土を手にしてから、ひたすら土を手にしてきた―上京、新制作派協会旗揚げ、シベリア抑留、憧れのパリでの個展など、決して平坦ではなかった自らの半生を、世界的彫刻家が質実に綴る。図版多数収載、年譜付。
目次
あこがれ
北海道(生まれ;夕張 ほか)
彫刻への道(上京;画塾通い ほか)
新制作協会(旗揚げ;仲間 ほか)
シベリア(満州へ;非常ラッパ ほか)
戦後(復員;四年ぶりの粘土 ほか)
著者等紹介
佐藤忠良[サトウチュウリョウ]
1912年、宮城県に生まれる。東京美術学校(現、東京藝術大学)彫刻科在学中に国画会展に初入選、国画会奨学賞受賞。39年、新制作派協会(現・新制作協会)彫刻部創設に参加。44年召集されて旧満州に渡り、翌年シベリアに抑留される。帰国後、市井の人々の素朴な美しさを表現した作風で制作を再開する。81年、パリの国立ロダン美術館で日本人初の個展を開催するなど、国際的な評価も高い。東京造形大学名誉教授。2011年没(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
nemuro
38
『掌の小説』(川端康成)に続く“しりとり読書”134冊目。札幌・芸術の森、大通公園、旭川・買物公園など道内各地の屋外常設作品も多く、馴染みのある彫刻家。美術館での個展にも何度か足を運んでいる。読みながら「帽子・夏」「オリエ」など各作品の記憶がふと甦った。1912(明治45)年生まれ、佐藤忠良の自伝。シベリア抑留など、決して平坦ではない半生。充分なる読み応え。2011年8月「くまざわ書店函館店」にて『一房の葡萄』(有島武郎)、『人生作法入門』(山口瞳)、『日本ぶらりぶらり』(山下清)などと一緒の購入だった。2025/07/15
かつみす
8
1988年に出た単行本を、2011年に亡くなった直後に再構成し文庫本として出版。佐藤さんというと、カンカン帽をかぶった少女像のように、静かなたたずまいのなかに生命力を湛えた彫像が思い浮かぶ。そんな作風からは伺えなかったのだけど、幼少時のこの人の家庭は相当に貧しかったし、子供が生まれてすぐに兵役で満州に飛ばされ、生死の際を彷徨ったあげく、シベリアで収容所暮らしを三年。順風満帆の人生ではまったくない。それだけに、戦後は何かを創りたいという気迫が人並み以上にあったのだろう。図版が多く収められた贅沢なつくりの本。2018/07/07
fubuki
4
戦時中の話は、ドラマや映画で見ることはあっても、自伝として読んだことがないような気がする。ドラマじゃない、現実があった。それでも決して悲壮感だけではなく、人生の思い出として記されていることに興味深く読んだ。画家(彫刻家)としての視野が広がった時だったのかもしれない。芸術で食べてゆくことは、並大抵のことではないだろうけど、諦めない心やユーモアを解する広い心が、豊かな作品性にも繋がったように思う。またちょっと違う気持ちで、忠良作品と対話できそうな気がする。2012/11/12
うぼん
2
印象的だったのは、パリ個展での好評を受け「具象彫刻は世界的に疲弊しているように見える」と、つまり自分が評価されたのは「周りが衰えてまずくなってしまったから」だというくだり。彫刻家の鋭い眼力による謙遜と危惧に慄く。 昔、宮城県美術館に佐藤忠良記念館が併設されてすぐの頃、平日に丸一日かけてゆっくりと作品鑑賞したことがある。その日小さな地震があって本館の防火扉が次々と落ちた。ちょうど記念館区域にいた自分は、忠良の作品に囲まれた無音の空間に偶然一人で隔離される形になった。15分程だったが永久とも思える時間だった。2023/05/11
ぶんぶん
2
シベリア抑留時のことがさらりと書いてあるのが逆に印象的だった。2012/03/20