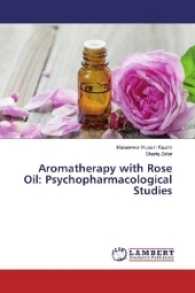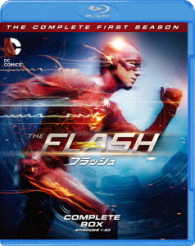内容説明
親指、爪、耳、眼、足…。身体のわずかな感覚の違いを活かして、ピアニストは驚くほど多彩な音楽を奏でる。そこにはどのような秘密があるのか?鋭敏な感覚を身につけるにはどうすればよいのか?モノ書きピアニストとして活躍する著者が綴る、ピアニストの身体感覚とは。
目次
1 ピアニストの身体
2 レガートとスタッカート
3 楽譜に忠実?
4 教えることと教わること
5 コンサートとレコーディング
6 ピアニストと旅
7 演奏の未来
著者等紹介
青柳いづみこ[アオヤギイズミコ]
ピアニスト・文筆家。安川加壽子、ピエール・バルビゼの両氏に師事。フランス国立マルセイユ音楽院首席卒業。東京芸術大学大学院博士課程修了。1989年、論文「ドビュッシーと世紀末の美学」により、フランス音楽の分野で初の学術博士号を受ける。90年、文化庁芸術祭賞受賞。演奏と執筆を両立させ、著書には『翼のはえた指 評伝安川加壽子』(吉田秀和賞)、『青柳瑞穂の生涯』(日本エッセイスト・クラブ賞)、『六本指のゴルトベルク』(講談社エッセイ賞)、などがある。大阪音楽大学教授、日本ショパン協会理事(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ひめか*
47
左親指の根元が陥没しているのは私も同じ。これから難曲を弾く上でネックになるから、早く治したいけどなかなか完全には治らない。親指の使い方が上手い人は演奏が上手い。指や腕のストレッチや力を抜く練習なども重要だと思った。音楽とはいえスポーツみたい。演奏会の朝は布団の中で曲を一通り頭の中で鳴らしてみるイメトレは効きそう。暗譜の仕方はいろいろ。視覚的、聴覚的、運動感覚的、頭脳的・分析的→演奏家によって異なる。私は指の感覚と耳で暗譜するから方法の多さに驚く。「音と言葉」コラム共感。物書きピアニストという肩書きいいな!2015/10/29
Miyako Hongo
18
ちょっとだけ、のつもりでめくったら止まらなくなった。音楽と文筆の二足の草鞋を履く筆者の本。 □心と体は繋がってて、身体感覚が違う人の考え方は独特だと思うので、ピアニストがどんな風に考えるかは興味ある。基礎教育専門で身体機能に造詣深いらしく、指や全身のストレッチ、マッサージや鍼灸の話が興味深かった。作曲家や演奏者、音楽教育の話題も豊富。でも一番は言語表現。「音を掴む」とか「音の粒立ち」とか、演奏者ならではの表現が新鮮。外来語の演奏用語より、こういう言い方の方がぐっとくる。2016/05/29
胆石の騒めき
17
(★★★☆☆)音楽教育を受けた人が読むと、より共感でき面白いのではないだろうか。しかし、著者の言うところの「クラシック界を神秘的な別世界のように感じていて、演奏家の秘密をほんのちょっとでも知りたい人」である自分にとっても十分面白い。「芸術作品は、心の動揺でできている」という言葉が印象的。「楽譜に忠実である」ことについても述べられているが、天才作曲家の情感が楽譜上に表しきれるとは思えない。その行間(?)を優れた感性で補い表現できる演奏家が、良い演奏家であり、その感性に魅かれて好きな演奏家が出来るのだと思う。2018/03/27
双海(ふたみ)
14
軽快なコラムに笑った。著者のキャラクターが出ていてにやける(笑) コンサートの打ち上げは、生ビールに限るとのこと。「打ち上げの一杯!がなかったら、とうにピアノ稼業から足を洗っていたに違いない」って(笑) ピアニスト兼物書きなので文士並みの足の踏み場もない部屋・・・(笑) しかし、初見のスピードには驚いた。「1週目は譜読み、2週目に暗譜して3週目にはもう上げてしまうのが普通」さすがプロ。2020/09/20
Bartleby
13
鍵盤を押せば音が鳴る(音量は変えられるにしろ、またペダルという補助的なものはあるにしろ)というわりと単純な楽器を相手に、ピアニストはどうやってあれほどの音色を弾き分けることができるのか。自身ピアニストである著者が、その身体操法の秘密に迫った良書。とにかく、全身でこれほど微妙な調整を行なっているという事実に驚愕。練習に毎日数時間を要するのにもうなずける。ただ単に難しい曲を演奏するから、という理由だけではなさそうだ。恐れ入りました。2022/09/07
-

- 電子書籍
- 底辺探索者の最速攻略 ~最弱が99の回…
-
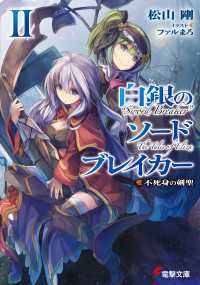
- 電子書籍
- 白銀のソードブレイカーII ―不死身の…