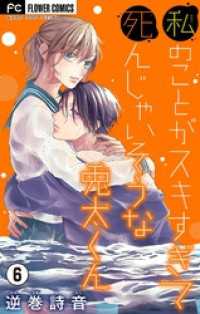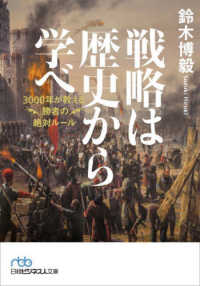内容説明
朝幕対立の時代に即位した青年天皇は徳川和子を妃に迎え学問と芸道を究める。幕府の莫大な資金を引き出しながら宮中の諸儀式を復させ、修学院離宮を造営する。“葵”の権力から“菊”の威厳を巧みに守りつつ、自ら宮中サロンを主宰、寛永文化を花開かせた帝の波瀾の生涯を描く評伝の決定版。
目次
1 下剋上の終焉
2 徳川将軍と天皇
3 寛永六年十一月八日譲位
4 寛永のサロン
5 学問する上皇
6 修学院造営
7 法皇登霞
著者等紹介
熊倉功夫[クマクライサオ]
1943年東京生まれ。東京教育大学文学部日本史学科卒業。日本文化史専攻。文学博士。京都大学人文科学研究所講師、筑波大学歴史人類学系教授を経て、92年国立民族学博物館教授。2004年退官、同年林原美術館館長、国立民族学博物館名誉教授。2010年静岡文化芸術大学学長。茶道史・寛永文化のほかに日本料理の文化史、民芸運動など幅広く研究(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
夜間飛行
175
後水尾の生い立ちは、下剋上(=身分否定)の終焉とその残滓として風俗に残されたかぶきの時代に重なる。父の後陽成は孤立し、家康の意で即位した後水尾を憎んで亡くなった。さらに禁中幷公家中諸法度の圧迫、紫衣事件で勅許を反古にされ、徳川の血を引かぬ皇子を殺されるなど苦労が絶えず、譲位して学問や歌に生きた。寛永の文化人との交流や、そこに形成されたサロンが興味深い。後水尾はこの人々の真ん中にいて身分を超えた関わりを持ったようだ。京所司代の板倉父子、松永貞徳や本阿弥光悦ら町衆、千宗旦や小堀遠州といった茶匠とも縁があった。2024/09/29
中年サラリーマン
19
戦国から太平の世、下克上から安定の時代である。その途中で権力とは一線をがす価値観を提唱しつづけた千利休は排除され、江戸の世となり行き場をうしなった者は傾奇者になった。新たに権力の座についた将軍は世の中の安定化に奔走する。そんな時勢に皇位を継承した後水尾天皇。幕府は支配を安定化するために強力に権力を発動する中、権威をはぎとられ意のままならない天皇はどういう生涯をすごしたのか。学問、芸術にのめりこみそしてそれによって上方の文化振興に貢献、また幕府への消極的な反抗の生涯はとても興味深い。2014/05/02
KAZOO
13
誰かの小説でこの天皇の名前が使用されていたので、読むことにしました。ちょうど徳川家が安定しつつあるときに、徳川家から皇后を迎えています。あまり注目されてはいない天皇なのでしょうが、結構したたかな人物であった感じがします。幕府から金を出させて、宮中の儀式なども復活させたり修学院離宮を造営したり文化人とのサロンを形成したことを見てもそれがうかがえます。面白い人だと思います。2014/02/25
maekoo
10
古典の享受史を学んでいると江戸時代の寛永文化の核となった後水尾院にも行き着く。 徳川家康・秀忠・家光と渡り合い、将軍家の徳川和子(東福門院)を中宮とし公家諸法度等の締め付けの中、莫大な財産によって、失われた伝統の復興を目指し、禁裏内の朝儀復興や古典復興と寛永文化隆盛に努めた希有な天皇と皇后であった! 宮中文化の集大成的、仙洞御所・桂離宮・修学院離宮等のサロンをハブとして、立花(生け花の祖)の流行や椿の品種改良ブームの仕掛け人であり、様々な多岐に渡る著作を著わした知れば知るほど面白い稀有な天皇でもあります!2024/10/22
きさらぎ
8
著者が後水尾院に心を寄せている事が伝わってくる文章で、何というかしみじみ院が愛しくなる(笑)「人物に興味があって、制度や経済には余り興味がない」と言い切るだけあって、東福門院、板倉重宗、近衛信尋、息子の後光明天皇といった、院を取り巻く人々の人物模様が次々に繰り出されてくるのが面白い。修学院離宮と大覚寺がどちらも大好きな私としては、修学院離宮が大覚寺を強く意識して営まれた、といった記述は嬉しかったなあ。後水尾院の許で、かなり自由な雰囲気の中で立花・茶・和歌などが楽しまれた寛永のサロンの雰囲気が伝わってきた。2019/11/08