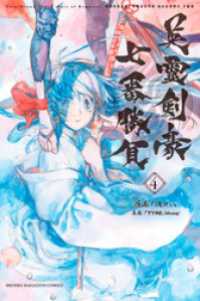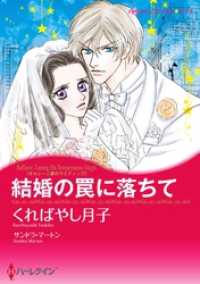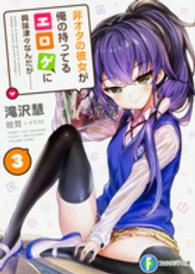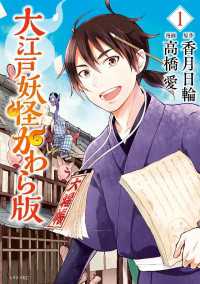内容説明
かつてこの国を生きた人々の生の輝きが、時代の扉を押しあけた―。歴史上の人物が持つさまざまな魅力を発掘したエッセイ百八十八篇を、時代順に集大成。第一巻には“人類普遍の天才”空海から、“魔術師”斎藤道三まで、司馬文学の奥行きを堪能させる二十七篇を収録。
目次
倭の印象
生きている出雲王朝
ああ出雲族
叡山
わが空海
『空海の風景』あとがき
高野山管見
ぜにと米と
平知盛
三草越え〔ほか〕
著者等紹介
司馬遼太郎[シバリョウタロウ]
大正12年(1923)、大阪に生まれ、大阪外語大学蒙古語学科を卒業。昭和34年『梟の城』により第四十二回直木賞を受賞。同42年『殉死』により第九回毎日芸術賞、同51年『空海の風景』など一連の歴史小説により第三十二回芸術院恩賜賞、同57年『ひとびとの跫音』により第三十三回読売文学賞、同58年「歴史小説の革新」により朝日賞、同59年『街道をゆく―南蛮のみち1』により第十六回日本文学大賞(学芸部門)、同62年『ロシアについて』により第三十八回読売文学賞(随筆・紀行賞)、同63年『韃靼疾風録』により第十五回大佛次郎賞を、それぞれ受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ポチ
57
エッセイ。出雲と義経の話がとても良かったなぁ。裏話的なところもあり面白く読了。2019/01/22
AICHAN
44
図書館本。「神韻ヒョウビョウ」ではあるが、やはりかつての日本列島はまず出雲族によって統治されていた。そこに天孫族がやってきて出雲族は平定されたと考えてよいと思った。出雲族が沿海州のツングース族を祖先に持つ民族の後裔だと感じさせる説は以前にも読んだが興味深い。また、司馬さんのお父さんと同じく空海は山師だとかつての私は思っていたが、『空海の風景』を読んでから考えが変わった。史上稀に見る天才なのだ、と。『空海の風景』のあとがきを読んで、あらためてそう思った。2019/01/22
金吾
33
○古代から戦国までのいろいろな人物について触れているエッセイです。幅広さに司馬さんの知識の凄さを実感します。やはり好きな戦国時代の話が好きな部分でした。2022/06/23
Kaz
29
「邂逅」とは「思いがけずめぐりあうこと」という意味だそうだ。司馬先生が手がけた作品、寄稿などをピックアップして古代から安土桃山時代までを集めたのが本書。空海、平知盛、斎藤道三、雑賀孫市、黒田官兵衛、秀吉という有名人、偉人、英雄から市井の無名な人々までのエピソードを追うことで、教科書とは違うアプローチで日本史を辿ることができる。改めて伝わって来たのは、司馬先生は秀吉贔屓であり、家康には好意を持っていなかったということ。やはり、司馬先生は大阪人だ。2018/04/29
かず
28
去年は「この国のかたち」全巻を読み、今年はこちら。前者に比べてさらっとした読後感。個人的には、もっと強い刺激の方が好み。興味深かった逸話は、倭の字義が「したがう、ゆだねる」というものであること。自分でも調べたことがあったが、これは分からなかった。勉強になった。日本人の特性は今も変わっていないということに驚く。それと、出雲国造が現代でも残っているという事。宮家の御姫様が千家家に嫁いだことが話題になったが、そういうお家柄とは初めて知った。2019/01/22