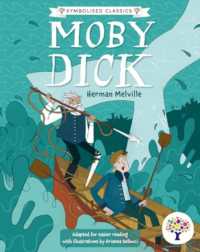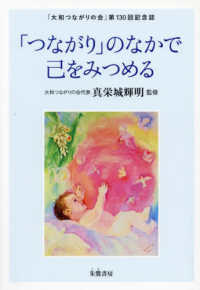内容説明
高揚した帝国主義時代のヨーロッパに、突如として現れた黄色人種脅威論。この漠たる不安が「黄禍論」として政治スローガン化し、各国を席巻した背景と経緯をたどる。膨大な資料をもとに欧米人の複雑な心理を明らかにし、豊かな歴史タペストリーとして織り上げた画期的労作。
目次
序章 黄禍論はどのようにして生まれたのか
第1章 黄禍論にたいするイギリスの貢献
第2章 黄禍論へのアメリカの関与
第3章 黄禍論を唱えるロシアの声
第4章 黄禍論にたいするフランスの視点
第5章 黄禍論をめぐるドイツの議論
著者等紹介
ゴルヴィツァー,ハインツ[ゴルヴィツァー,ハインツ][Gollwitzer,Heinz]
ドイツを代表する近・現代史家。1917年ニュルンベルグ生まれ、ミュンヘン育ち。ミュンヘン大学で博士号と大学教授資格を取得し、57年から82年までミュンスター大学で歴史学の教授をつとめる。99年没
瀬野文教[セノフミノリ]
翻訳家。1955年東京生まれ。北海道大学独文科修士課程卒。DAAD(ドイツ学術交流会)給費生としてケルン大学に留学。現在はドイツ語塾トニオ・クレーガーを経営(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おはぎ
10
「黄禍」がどのような理由から生まれどのように展開したか丹念に追っていく本。ヨーロッパ各国ごとの黄禍に対する温度差など面白い。安い労働力や高い出生率など今の一部の人による外国人への「懸念」言論と似ているところもある。追記:ヴィルヘルム2世が良くも悪くもキャラが濃すぎる。2024/09/13
HANA
5
日清戦争前あたりから第一次世界大戦後まで帝国主義のアメリカ、ヨーロッパで黄色人種がどのように捉えられていたかを論証している。アメリカ、イギリス、フランス等国ごとに考証されているが、その中でも各人考え方が違いひとまとめに捉えにくい。思うに黄禍とは鏡みたいなものだと思う。今まで自分がしてきたことをやり返されるという恐怖感がベースにあるのではないか。あと中国の安い賃金によって自国の産業が圧迫されるという不安は今も昔も変わっていない。2011/08/04
廉子
1
西洋社会に大人数で押し寄せる中国と、同じ土俵に上がって来た日本への不安。征服を繰り返して繁栄した文明・時代だからこそ、今度は自分達が征服されるのではないかという恐怖。東洋という、西洋とは全く違う価値観を持つ文明への無知。全体を通して感じられたのはこの3つ。あとドイツは他のヨーロッパに比べてまだ植民地の獲得欲が強く、アメリカでは黒人開放後に黒人にとって変わったのが中国人で、そこから黄禍論、中国人排斥運動が起きた。中国人の数で押して来る感じは現代でも同じだと思う。2011/04/05
ptyx
0
★★★☆2011/12/14
dogu
0
他者を啓蒙しているつもりの人、恐怖と不安で他者を操ろうと している人が何時の間にか自分自身でもそれを信じこむ過程を 見せてくれている。ツィンメルマン電報事件の遠因がここに在った。2011/04/21
-

- 和書
- 口上人生劇場青島秀樹伝