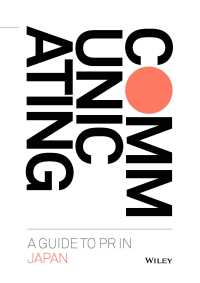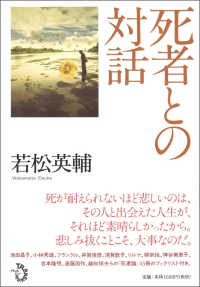内容説明
中世から第二次世界大戦に至るまでのヨーロッパで起こった戦争を、テクニックだけではなく、社会・経済・技術等の発展との相関関係においても概観した名著。二〇〇九年に改訂された新版の本邦初訳。
目次
第1章 封建騎士の戦争
第2章 傭兵の戦争
第3章 商人の戦争
第4章 専門家の戦争
第5章 革命の戦争
第6章 民族の戦争
第7章 技術者の戦争
著者等紹介
ハワード,マイケル[ハワード,マイケル][Howard,Michael]
1922年生まれ。オックスフォード大学卒業。イギリスの歴史学者。国際戦略研究所(IISS)名誉所長。ロンドン大学の戦争学部の創設に携わり、戦争史の世界的権威で、クラウゼヴィッツ研究の泰斗としても知られている
奥村房夫[オクムラフサオ]
1915年生まれ。陸軍士官学校・陸軍大学卒。戦後、早稲田大学大学院博士課程修了。元拓殖大学・秋田経済大学教授
奥村大作[オクムラダイサク]
1943年生まれ。ロンドン大学大学院修士課程修了(M.Sc.)。日本大学教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Francis
14
五年間積読していた本。面白かった。ただ、内容はもう少し詳しく書いても良いのでは?戦争が当時の社会や経済の構造と密接に繋がっていることがよく理解できる。著者が影響を受けたクラウゼヴィッツ「戦争論」を読めばもっと良く理解できるかも。2018/10/17
無重力蜜柑
11
中世〜第二次大戦までのヨーロッパの戦争史。アメリカや日本やオスマン帝国はほぼ出ない。歴史家が書いただけあって戦術や兵器の発達、詳細よりは当時のヨーロッパ社会の文化、政治、経済状況と戦争という現象の連関に多くの筆が割かれている。訳者も指摘している通り、技術の役割がかなり小さく評価されているのが特徴か。重商主義の戦争観や軍人階級の社会的基盤など面白い論点は多かったが、全体的にトピック別で時系列をバラバラにしてまとまっており、捻くれた言い回しや訳文のぎこちなさもあって読みにくかった。馴染みのない前近代は特に。2022/05/28
白義
9
戦争と社会史の相互関係をしっかりした文章で描いた通史。経済や文化的な基盤の変化が戦争をどのように変え、またその戦争が社会をどう変えていったのかを、戦術史や兵器の解説も漏らさずこの分量にまとめたのが凄い。騎士的な思想と慣行が支配した中世から商人や専門軍隊の近代へと合理化が進むようで、国民という階層の出現により一挙に規模と熱気が激化していく転換が見所。戦史、軍事関係の基本書の一つ足りうる。陸海軍に比べ空軍の発展は当然ながらかなり遅れたが、その躍進の理由が国民の戦争参加というのに納得2013/03/02
bapaksejahtera
8
表題の通り近世以降欧州における戦争史であるが、記述は戦史には留まらない。戦争社会史政治史経済史、技術史等に考察を加え、まさにその結果として以下の章分けが成立する。封建騎士の戦争、傭兵の、商人の、専門家の、革命の、民族の及び技術者の戦争がそれであり間然する所がない。社会主義が凋落しお花畑平和主義と変貌した我が国ではこういう学問は成立しないのだろう。密集歩兵と槍兵、先込銃からライフル等の技術論、兵站革命と銃後、国民国家と戦争動機づけの変容等話題は果てしない。惜しむらくは父、老大家によると見られる翻訳が硬い。2020/05/19
flat
7
ヨーロッパにおいて騎士や傭兵、商人や技術に焦点を当てて各章毎に書いている。しかし時代が現代に近付くに連れてその規模は大きくなり且つ水爆などの核の破壊力はミサイル技術によって至る所へと届けられるようになっている。最終章の最後に一千年の間ヨーロッパで理解され実行されてきたような戦争は、もう終わったのだろうか。という言葉で締められているのが印象に残った。2019/04/21