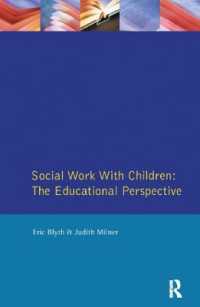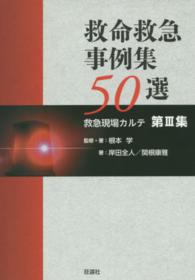出版社内容情報
ユダヤ教が拡がるイスラエル、日本まで伝播したペルシア文明、芸術の華開くヘレニズム世界。各王朝の盛衰を、考古学の成果をもとに活写する。
内容説明
ペルシア戦争やバビロン捕囚、アレクサンドロス大王の遠征等、諸王朝が周辺の民や地域を巻き込んで覇を争った地中海アジア。さらにユダヤ教やペルシア文明が拡がり、ヘレニズム芸術が華開いた劇的な歴史を考古学の成果をもとに詳説する。
目次
1 地中海アジアの夜明け
2 諸民族のめざめ
3 イラン高原とその住民
4 アケメネス朝ペルシアの成立と発展
5 地中海アジアの隷属
6 ヘレニズム時代の人々
7 パルティア王朝―第二イラン王朝
8 ローマの東方進出
9 サーサーン朝ペルシアの興亡
10 地中海アジアの終末
著者等紹介
小川英雄[オガワヒデオ]
1935年、神奈川県に生まれる。慶應義塾大学文学部史学科卒業後、ロンドン大学、ユトレヒト大学に留学。イスラエル、イギリスで発掘調査に従事。現在、慶應義塾大学名誉教授。文学博士。専攻は古代オリエント、ローマ帝国
山本由美子[ヤマモトユミコ]
1946年、北海道に生まれる。東京大学文学部卒業後、同大学院、ロンドン大学東洋アフリカ学院を修了。現在、川村学園女子大学文学部史学科教授。専攻はゾロアスター教史、古代イラン史。インドに移ったゾロアスター教徒であるパールシーの歴史にも関心を持つ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Mzo
10
隙間時間でゆっくり読んだため、最初の方は既に忘れてしまった…って、初読の時も同じようなこと書いてた。オリエント史と相性悪いのか?2018/06/27
MUNEKAZ
9
手堅い内容の一冊。小川氏がメソポタミアやシリアなどオリエントの西部を、山本氏がペルシャを担当している。前者は発掘された遺跡の紹介が多くちょっと硬い印象。それに対し後者は、アケメネス朝・パルティア・ササン朝とイランに起こった各王朝を一つなぎに捉えて解説しており面白い。イランなんてイスラム化したとはいえ、現在も地域大国として強い影響力を持っているのだからしぶとい存在である。また近年の中東の動乱の中で、紹介されている遺跡のどれだけが無事なのだろうかと気になってしまった。2019/02/13
coolflat
8
世界の歴史1の続き。古代オリエント史の後半。本書で主となるのは、アケメネス朝以降、パルティア、ササン朝。146頁。“古代ペルシア語は、ダレイオス1世の時でさえ、公式の文書や碑文以外には使用されなかった。当時のオリエント世界の共通語は、バビロニアやアッシリアで使われたアッカド語であったが、ペルシア帝国内の事務的または実用的な文書にはエラム語が用いられた。しかも共通語は、より簡単で覚えやすいアルファベットを使うアラム語にかわりつつあった。ペルシア帝国の共通語がアラム語になるのは、紀元前4世紀初めのことである”2016/03/27
Hiroshi
4
オリエントとは古代ローマから見て東方にある世界。エジプト、メソポタミア、ペルシアだ。第1巻でエジプトとメソポタミアを扱ったので第4巻では地中海アジアとペルシアを中心に扱う。此所には多くの人種が集まる。①ヒクソス、②ヒッタイト、③フリ、④海の民、⑤ペリシテ、⑥チェケル、⑦アラム、⑧フェニキア、⑨ヘブライ、⑩フリギュア、⑪リュディア、⑫イラン、⑬エラム、⑭スキタイの説明がなされる。西アジアのセム系、インド・ヨーロッパ語族、騎馬民族、遊牧民、雑多の人種の集まりと色々である。遊牧民は定住しておらず勝手に移動する。2022/11/12
tieckP(ティークP)
4
2人の著者によるもの。山本氏がイランを中心としたアケメネス朝ペルシア・パルティア・ササン朝ペルシア、小川氏がそれより西のメソポタミアや地中海周辺地域について。前者はベーシックな作りで、著者の主張は、ササン朝がアケメネス朝を継いだと主張しているけど実際はパルティアもこの系譜からさほど離れていない国家なので連続して見るべきだ、ということ。後者は考古学の色が強くて、ときおり、歴史説明の補強に遺跡を使うのではなく、遺跡を紹介することが目的化していたので、線ではなく点の説明に感じたけど、博識さは迫力として伝わった。2016/11/01