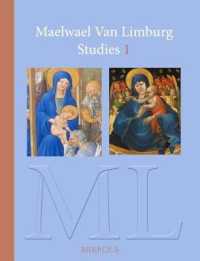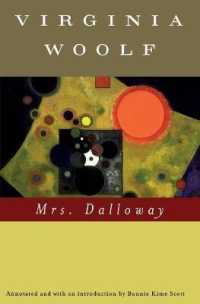出版社内容情報
古来西洋と東洋の交易の中継地として、特色豊かな数々の文化を発展させた東南アジア諸国。先史時代から20世紀までの歴史を豊富な図版とともに詳説。
内容説明
古来より東西交易の中継地として海のシルクロードを発展させ、多様な文化が開花した東南アジア諸国。ボロブドゥルやアンコール・ワットなど壮麗な遺跡を残した豊饒な歴史を、先史時代から二十世紀にわたり詳説する。
目次
1 東南アジア史の曙
2 インド文明の伝来と国家の形成
3 古代「海のシルクロード」
4 東南アジア群島部における国家の発展
5 東南アジア古典世界の栄華に向けて―十三世紀までのインドシナ半島
6 中国船の来航と東南アジア群島部
7 歴史の大転換―十三世紀以降のインドシナ半島世界
8 イスラーム国家の形成
9 東南アジア群島部の「商業の時代」
10 東南アジア群島部における「商業の時代」から「開発の時代」へ
11 インドシナ伝統社会の変貌―近代への胎動
著者等紹介
石澤良昭[イシザワヨシアキ]
1937年、北海道生まれ。61年、上智大学外国語学部卒業。文学博士。パリ大学学術高等研究院で碑刻学を学ぶ。上智大学教授、外国語学部長を歴任し、現在、上智大学長。アンコール王朝史を専攻。61年よりフランス極東学院P・グロリエ教授に師事。91年にカンボジア人保存官の人材養成を開始、2001年、考古研修中に二七四体の仏像を発掘。07年にアンコール・ワット西参道を修復し、シハヌーク・イオン博物館をイオン(株)の協力を得て建設。03年、国際交流基金賞受賞、07年、カンボジア国王よりサハメトリ賞を親受
生田滋[イクタシゲル]
1935年、旧満州国ハルビン市生まれ。59年、東京大学文学部東洋史学科卒業。61年、同大学院人文研究科修士課程(東洋史専攻)修了。財団法人東洋文庫付置ユネスコ東アジア文化研究センター研究員、同調査資料室長、大東文化大学教授を経て、同大学名誉教授。東南アジア近現代史および大航海時代史を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
MUNEKAZ
coolflat
KAZOO
つだしょ
じょあん
-

- 洋書電子書籍
- ダーウィン書簡集 第26巻:1878年…