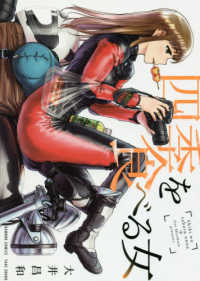出版社内容情報
草原の小さな一部族から史上最大・最強の大帝国となったモンゴルの文化・経済・生活を活写。
内容説明
広大なユーラシア大陸を縦横無尽に疾駆した蒼き狼の群れは、たぐいまれな統治システムと柔軟な経済政策で世界史上最大の連邦国家を築いた。好戦的と思われがちな草原の民=モンゴルの知られざる実像を生き生きと描き出す。
目次
第1部 はるかなる大モンゴル帝国(世界史が世界史となるとき;蒼き狼たちの伝説;世界文明への射程;めぐりあう東西;近代世界の扉)
第2部 モンゴルとイスラーム(チンギス・ハンの王権神授説;チンギス・ハンと預言者ムハンマド;チャガタイ家とバルラス家;チンギス・ハンとオグズ・ハン;チンギス・ハンの遺産)
著者等紹介
杉山正明[スギヤママサアキ]
1952年、静岡県に生まれる。74年、京都大学文学部卒業。79年、同大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。現在、京都大学大学院文学研究科教授。中央ユーラシア史、モンゴル時代史を専攻。2003年に司馬遼太郎賞、06年に紫綬褒章、『モンゴル帝国と大元ウルス』(京都大学学術出版会)で07年に日本学士院賞を受賞
北川誠一[キタガワセイイチ]
1947年、北海道に生まれる。70年、北海道大学文学部卒業、72年、同大学大学院修士課程修了。北海道大学助手、弘前大学人文学部教授を経て、東北大学大学院国際文化研究所教授。西アジア史、コーカサス史を専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
KAZOO
じょあん
tieckP(ティークP)
Zhao