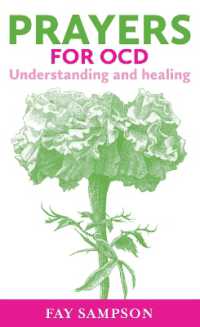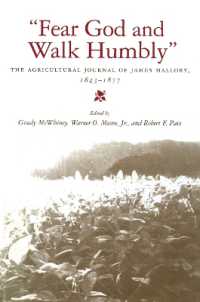出版社内容情報
グローバル化によって衰退する組織原理。国家や企業を離れ、茫漠とした「地球社会」のなかに曝される現代人に、心の居場所はあるのか。〈解説〉三浦雅士
内容説明
グローバル化によって衰退する組織原理。国家や企業を離れ、茫漠とした「地域社会」のなかに曝される現代人に、心の居場所はあるか―。「社交」の復権による新しい人間学の誕生。
目次
社交への飢餓
現象としての社交
社交の社会学
社交と現代社会論
社交と遊戯
「アルス」の終焉
社交の興亡
社交と経済
社交と政治
社交と文化、文明
社交と自我
グローバル化と社交社会
著者等紹介
山崎正和[ヤマザキマサカズ]
1934年、京都に生まれる。京都大学文学部哲学科卒。大阪大学教授、東亜大学学長等を経て、LCA大学院大学学長。劇作家・評論家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
アナクマ
25
「社交」を掘り起こす。茫漠たるグローバル社会に溶ける血縁地縁。軽くなる組織縁。拮抗するのは選び取る縁で、そこでのふるまい・関係性=社交と理解。◉終章。国家や組織への帰属感が薄れ、新たな身元証明と隠れ家が必要に。そこで、組織ではなく個人相互の評価が絆として用いられ、贈与に名誉が伴う営みの再興を予測(名誉って食えるの?という反射は置く)。SNS黎明期の2003年に「第三の道は信用社会」と結論。◉ただし社交を引き受けるには「ひとりの自己、プロフェッショナリズムの観念が必要」だという。楽じゃないす。2019/05/18
ryota
5
特に近代以降、工業社会、ポスト工業社会の文明論。今まで読んだ文明論の中で、一番、現状を言い当ててる内容だと思う。説明も丁寧で面白い。提案も実感として受け入れやすく後ろ向きでない。今どきの文明論は、後ろ向きか、アクロバティックな前向き(個人的にはそう感じる)が多い中、地味ながら地に足の着いた論考が展開されていて、かなり良い本。2015/01/12
station to station
4
人間の本質は社交にあるという事実を、政治や経済から文化論に至る非常に広範な知見を動員して論じている。近代社会を駆動してきた(明確な規則や制度、階層構造を持った)企業や国家を中心とする「組織」の原理に対し、信用や贈与のような要素を持った「社交」という関係性が、グローバル化が進展した現代にあって重要性を増しているということが指摘される。また、生活のリズムを能動的に統御するか、流されるままに生きるかという点で、前者を文明、後者を自然と定義し、両者の間で絶妙な均衡を取れたときに文化が生まれるという議論も興味深い。2020/04/18
youco
3
「社交」について、社会学的見解だけでなく、歴史的、文化的に論じされる。読み応えも充分で、とても勉強になった。最後のグローバリゼーションと終章は「フラット化する世界」の方がまとまっている2008/06/27
学生
2
赤本に出てきた。2023/02/16
-
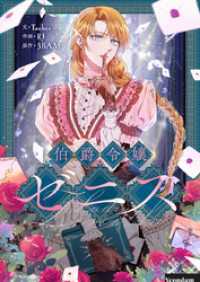
- 電子書籍
- 伯爵令嬢ゼニス【タテヨミ】第41話 p…