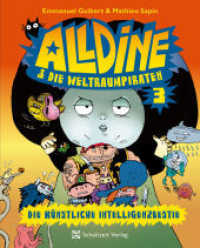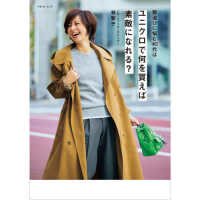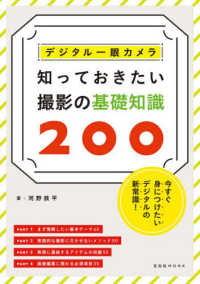内容説明
理想を追って、挫折と漂泊のうちに生きた孔子。中国の偉大な哲人の残した言行は、『論語』として現在も全世界に生き続ける。史実と後世の恣意的粉飾を峻別し、その思想に肉薄する、画期的孔子伝。
目次
第1章 東西南北の人(伝記について;聖人ののち ほか)
第2章 儒の源流(伝統について;大儒と小儒 ほか)
第3章 孔子の立場(体制について;群不逞の徒 ほか)
第4章 儒教の批判者(批判について;ギルド的集団 ほか)
第5章 『論語』について(文体論;儒家八流 ほか)
著者等紹介
白川静[シラカワシズカ]
1910(明治43)年福井県生まれ。立命館大学名誉教授、文字文化研究所所長。43年立命館大学法文学部卒。84年から96年にかけて『字統』『字訓』『字通』の字書三部作を完成させる
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
イプシロン
43
本当に感動した著作の感想はすぐには言葉にできない。言葉にならないのだ。それでもキーボードーに向かう愚かさよ。本文を読みつつ何度も深く吐息し、沈思黙考した。だが先へと進むと、先に沈思黙考して辿りついた以上の深い哲理が示され、またしても沈思黙考せざるを得なかった。そうしてあとがきを読み終えたとき、感想など書けない次元の絶望感に打ちひしがれた。しかし、それこそが白川静が用意した場所であり、著者が望んだのは読者一人一人がその絶望から歩みだす勇気を持って欲しいという願いに似たなにかなのだろう。『論語』を、2020/10/02
うえぽん
40
中国古代文学・文字の大家が、歴史的事実に即して孔子とその弟子達、批判者達の実像に迫った書。父親の名も知れぬ巫女の子であった孔子は、長らく亡命者であり、政治的手腕はなかったが、その偉大な人格ゆえに、弟子達が言行を記録した。その最も忠実な記録とされているのは論語だとするが、それでも編纂期も編者も不明で、古典として読むことの困難さが理解できる。論語を倫理道徳を中心とした格言集的なものと捉え、五経などを統治に関する官僚の必読書とされたイメージを脱し、伝え残る言葉を発した孔子の実際の境遇に想いを至らせる画期的作品。2024/03/03
傘緑
27
「孔子の言動には、人が夢みるときのような、何か美しいものを感じさせる…また、何かの幻影に怖れおののくような姿がある」この本は『伝』であり『論』ではない。呪者・白川静は「権威をもって、それも穏やかな権威をもってすべてを語っている(ボルヘス、オラル)」。巫女を母として呪の世界に生きた世界最古の思想家・孔子、彼は挫折した革命者であり、政治家であった。その敗北と亡命、流謫、「殺すもの咎なし」という死に裏打ちされた絶対の自由の内で、始原の思想は築き上げられた。「思想は始原において、矛盾と魔性を孕んでいる(呉智英)」2016/10/29
Tomoichi
23
宮城谷昌光の「孔丘」を買うはずが、白川静先生のこっちを買う。いつも通り先生の本は難しいが、リアルな孔子や儒教ってこうだったのかって読ませる。もう少し支那古代思想の知識がないと先生の本は読み込めない。不甲斐ない自分です。2023/12/30
ひよピパパ
21
東洋学の巨知、白川静氏による孔子評伝。古代文字文化への深い洞察から孔子の実像を描き出す。「孔子の世系についての『史記』などにしるす物語は、すべて虚構」「『老子』が『荘子』より後の成立」「儒家に対するきびしい批判者とされる荘子は、その精神的系譜からいえば、むしろ孔子晩年の思想の直系者であり、孟子は正統外の人」など、見解が結構ラジカル。自身の持っていた固定観念が揺さぶられて刺激的だ。類似する事柄を何度もなぞりつつも、なぞるごとにより深く掘り下げていく論の展開は圧巻。やや難解だが読みごたえあり。2020/05/07