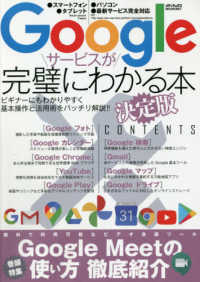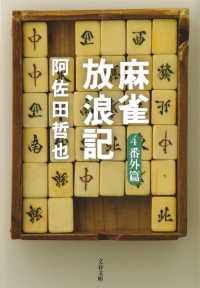内容説明
日本国体の至高を謳うだけではなく、戦争術発達の極点に世界統一・絶対平和を視た石原莞爾。使命感過多なナショナリストであると同時に、クールな現実認識をあわせもつ彼の軍事学論・戦争史観・思索史的自叙伝を収録。
目次
第1篇 戦争史大観(戦争指導要領の変化;会戦指揮方針の変化;戦闘方法の進歩;戦争参加兵力の増加と国軍の編成;将来戦争の予想;現在に於ける我が国防)
第2篇 戦争史大観の序説(別名・戦争史大観の由来記)
第3篇 戦争史大観の説明
著者等紹介
石原莞爾[イシハラカンジ]
1889‐1949。山形県生まれ。陸軍大学卒業。陸大教官などを経て関東軍参謀。欧州戦史研究と日蓮信仰から、日本を世界の盟主にとの使命感を得、世界最終戦争論を樹立。その第一段階として、満州事変を主導した。参謀本部作戦課長時代、満州国と一体となった総力戦体制ができていないと日中戦争不拡大を主張。東条英機と衝突し、第16師団長を罷免され予備役となる。その後東亜連盟を指導。敗戦後は全面的武力放棄を唱え、故郷で開拓生活を送った
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
双海(ふたみ)
17
日本国体の至高を謳うだけではなく、戦争術発達の極点に世界統一・絶対平和を視た石原莞爾。使命感過多なナショナリストであると同時に、クールな現実認識をあわせもつ彼の軍事学論・戦争史観・思索史的自叙伝を収録。(カバーより)2014/05/29
白義
14
その終末論、SF的な予言に目を眩まされがちだが、最終戦争以前に限れば、石原自身の戦略論、戦史観は、ルーデンドルフ等の影響深い「時代の子」と評するのが的確なものであり、本書はむしろフリードリヒ大王以来の近代戦史を、分かりやすく一貫性を持ってまとめたところに大きな価値がある。武力第一の決戦戦争と政治の延長としての持久戦争という分類で前者のもたらすヴィジョンに憑かれるのも、クラウゼヴィッツの「絶対戦争」辺りから潜在的にあったその軍事学(というかその弁証法史観?)の落とし穴みたいなものだろう2014/04/19
Yoshito Tsujii
4
過去の戦争から将来の決戦戦争、つまり日米を中心とした最終戦争が起きると予想する。その防衛策として満州の重要性を説く。また、決戦戦争では作戦目標は国民であり、空中戦が主体になると喝破している。満州事変を起こした張本人であり、石原莞爾に対する評価は様々であるが、彼の思考能力、予測能力がずば抜けていたことが本書から読み取れる。2013/06/06
さしとおう
2
最終戦争を見据えて国民皆兵の重武装国家を目指す可能性が日本にあったとは。2009/07/08
まふ
1
天才的軍略家と称された石原莞爾の著作。ヒトラー現役時代のことであるため、彼は天才ということになっている。フリードリヒ大王、ナポレオン、モルトケなどの軍事戦略を分析し線から面、最後は体という流れを整理しこれに勝つものによって最終戦争は終了するという考え方である。納得的な部分が無いことはないが、軍人の戦略とは実に即物的、かつ単純のような気がする。2004/08/25