内容説明
レーニン賞など数々の栄誉に輝く世界的作曲家が、死後国外での発表を条件に、スターリン政治に翻弄された芸術家たちのしたたかな抵抗と過酷な状況を語る。晩年に音楽学者ヴォルコフが聞き書きして編んだ、真摯な回想録。
目次
1 真実の音楽を求めて
2 わが人生と芸術の学校
3 ロシア革命の光と影
4 非難と呪詛と恐怖のなかで
5 わたしの交響曲は墓碑である
6 張りめぐらされた蜘蛛の巣
7 ロシア音楽の伝統を受け継いで
8 過去と未来の狭間
-
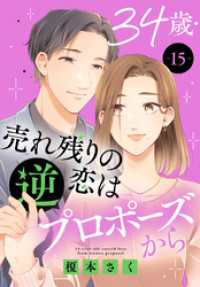
- 電子書籍
- 34歳・売れ残りの恋は逆プロポーズから…
-

- 電子書籍
- 限界OLさんは悪役令嬢さまに仕えたい(…
-

- 電子書籍
- 後輩OLはメイドのひなさんなんかじゃな…
-

- 電子書籍
- 女優バレリーナ vol.1 グラビ@シ…
-
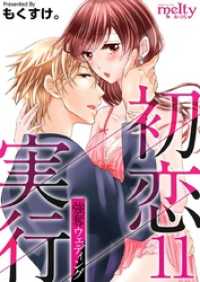
- 電子書籍
- 初恋実行~強奪ウェディング~ 11巻 …



