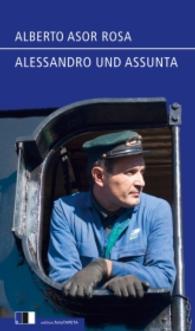内容説明
昭和十一年、磯部浅一、村中孝次、安藤輝三ら日蓮主義の青年将校たちが蹶起し、二・二六事件勃発。彼らが目ざした終着点とは一体何だったのか。鎮圧に回った石原莞爾を始め、木戸幸一、真崎甚三郎、武藤章らの手記を基に新資料も交えて事件の全貌に迫る。日蓮主義者たちの行動を軸に、日米開戦、敗戦へと突き進む昭和史のクライマックスを捉え直した力作。
目次
蒲田名物知ってるか
軽燥の法鼓
戦う幕僚たち
順逆不二
逃亡者
法華転
ハガキを書きました
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
筑紫の國造
7
下巻は「死のう団」から主人公の死まで。上巻では良い点を書いたので、今度は欠点を。まず、時間の前後が激しい。かなり頻繁に過去のことを述べたり未来に飛んだりするので、混乱してしまう。また、やはり仏教用語などが分かりづらい。著者は丁寧に解説してくれているのだが、経文などにルビもないため読みづらく、理解を妨げる。この作品のキモなので、丁寧過ぎるほど解説してもいいと思う。そして「なぜ日蓮主義が昭和史を動かす一要素になったのか」がいまいちはっきりしない。ところどころに書いてはあるのだが、長編なので総括が欲しかった。2016/12/09
ポン・ザ・フラグメント
3
『邪宗門』がいけないとは言わないけどさ、国柱会とかよりもずっと大本教のほうばかり見ていた感じはあるんだよな。まあ、オカルト的視点からもそっちのほうが面白かったし。日蓮主義が日本を動かしたというより、集団無意識的な流れの表層に日蓮主義が浮かんでいたというべきではないのかと思う。キリスト教のほうだって1930年代の幕屋運動とか、日本全体になんかそういう雰囲気があったのではないか。日蓮主義だけ抜き出すとまるで陰謀論のように見えるが、そんな合目的なものではなかったんじゃないかねえ。2015/10/26
ごん
0
終盤20ページくらいがものすごく美しい&自分がずっと考えてたことに重なってくる記述があって、蜃気楼が遠のいていくような静かでさらさらした崩落感に、本を閉じて嘆息。多分、何も清算されてないんだなぁ。ずっと続いてるんだなー…という気持ちになってしまった。2015/05/25
hamham
0
上巻での日蓮主義に「不気味」「凶暴」といったイメージを付与するような筆から変わり、意外にも下巻では日蓮主義への筆はまろやかである。私は二・二六事件の青年将校らへの興味からこの本を読んだので、彼らに関する頁の少ない点に物足りなさを感じた。磯部、村中、安藤など青年将校は日蓮主義だと書かれているが、それはおおよそ北一輝の影響の範疇を出ないものではなかったかと思われる。著者が日蓮と石原莞爾のことを快く思っていないことはすごく伝わってきた!私自身日蓮がどうも苦手なので、法華経≠日蓮と知れてよかった。2013/11/21
NyanNyanShinji
0
戦前昭和を軍国に変えた事件、神兵団事件、満州事変、五・一五事件、血盟団事件、二・二六事件。これらの事件は田中智学、井上日召、北一輝、西田税、石原莞爾らをはじめとした日蓮宗徒達の影響を抜きに語ることはできない。本書は架空のジャーナリスト「改作」を狂言回しの主人公として近代日蓮宗を腑分けしてゆく。人物の紹介や文献の引用による脱線でテンポが少々崩れるところもあるけど大変な力作だった。特に下巻終わり1/3辺りからの怒涛の展開には驚いた。また日蓮宗よりも法華経そのものに興味が湧いた。2022/11/21