出版社内容情報
正しく文学作品を鑑賞し、美しい文章を書こうと願うすべての人の必読書。文章入門としてだけでなく文豪の豊かな経験談でもある。〈解説〉吉行淳之介
目次
1 文章とは何か(言語と文章;実用的な文章と芸術的な文章 ほか)
2 文章の上達法(文法に囚われないこと;感覚を研くこと)
3 文章の要素(文章の要素に六つあること;用語について ほか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
おつまみ
47
文章って難しい。けど、実生活では絶対に必要になってきた。その中で、句読点が気になるけど、読む人が見やすい場所に打てばいいのではないかと思った。ただ、論文だと見る先生が文法に厳しいこともあるので、その場に応じた書き方が必要な気がする。実際に文章を書く機会は山ほどあるけど、場所が違って、どこで書くかも違う。2021/04/08
つちのこ
45
拙く、下手な文章に辟易としながらも日々撒き散らしている。私の文章に触れた人にとっては迷惑この上ないが、書くことが好きなのでやめられない。本書はそんな饒舌な自分にも、「しっかりした文章をどう書くのか」という、経験談からの論理的な視点で気づきを与えてくれる。日本語がもつ特性や品格をどう文章に活かすのか、いくら考えても浮かばない。才能やセンスを除いてできることは、正確な技術を学ぶことだろう。谷崎が冒頭に寄せた本書の目的「われゝ日本人が日本語の文章を書く心得」は、言い得て妙。90年の時を経ても色褪せない。2025/01/10
かわうそ
44
文章を上達するには「しかも研けば、研くほど、発達するのが常であります。そこで、感覚を研くのにはどうすればよいと云うと、出来るだけ多くのものを、繰り返して読むことが第一であります。次に実際に自分で作ってみることが第二であります。右の第一の条件は、あえて文章に限ったことではありません。総べて感覚と云うものは、何度も繰り返して感じるうちに鋭敏になるのであります。……文章に対する感覚を研くのには、昔の寺子屋の教授法が最も適している所以が、お分かりになったでありましょう。講釈をせずに、繰り返しゝ音読せしめる、2022/10/07
おさむ
40
文豪谷崎センセイの文章教室。日本の数多ある読本の定番ですね。大切な箇所はゴチックになっているのも親切です。例えば、文章を声に出してスラスラ読めるか試してみる。文法に囚われらない。感覚を研く。分かりやすい語を選ぶ。饒舌を慎む。言葉遣いを粗略にしない。敬語や尊称を疎かにしない‥‥。学生さんの入学祝いなどにはいい本かもしれません。2018/10/10
touch.0324
40
序文に《われわれ日本人が日本語の文章を書く心得》とある通り、論旨は作文の技巧ではない。文章の要は余計な飾り気を除いて実際に必要な言葉だけで書く(華を去り実に就く)こと。言葉や文字で表現出来ないことの限界(日本語の語彙の少なさ)を知り、字面と音調(感覚的要素)を利用して表現の不足を補うこと。感覚を磨くには名文を出来るだけ多く、暗誦できるくらいに繰り返し読むことと、自分で実際に作ってみること、とある。日本人と日本語の特性を理解し、こだわりをもって文章を作ろうと思う。美文家への道は遠い。2014/10/17
-
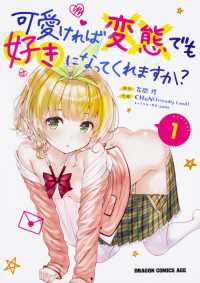
- 電子書籍
- 可愛ければ変態でも好きになってくれます…
-
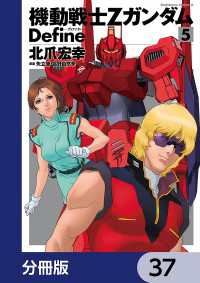
- 電子書籍
- 機動戦士Zガンダム Define【分冊…
-
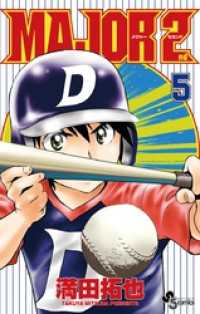
- 電子書籍
- MAJOR 2nd(メジャーセカンド)…
-
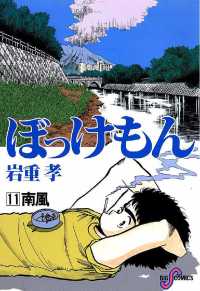
- 電子書籍
- ぼっけもん(11) ビッグコミックス





