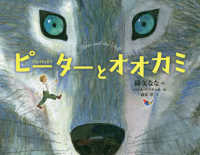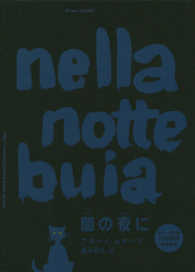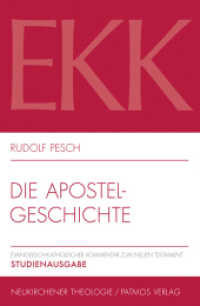内容説明
初夏のモスクワで4年に1度、1ヵ月間にわたって催されるチャイコフスキー・コンクール。この世界で最も権威ある国際音楽コンクールの審査員として、これまで触れられることのなかった舞台裏を描くとともに、国際化時代のクラシック音楽の現状と未来を鮮やかに洞察する長篇エッセイ。1989年度大宅壮一ノンフィクション賞受賞作。
目次
1 スーパースターの誕生
2 神童からコンクールの時代へ
3 コンクールが始まる
4 採点メモから
5 長期戦における兵站の話
6 ランダルたちの運命
7 女性ピアニストたち
8 「ハイ・フィンガー」と日本のピアニズム
9 なぜバッハをショパンのように弾いてはいけないのか
10 コンクール優勝者が多すぎる
11 コンクールの時代のクラシック音楽
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
192
第20回(1989年)大宅壮一ノンフィクション賞。 チャイコフスキーコンクールのピアノ部門の 審査員として 参画した 著者の視点は 新鮮で 面白い。冷戦時代のソビエトで、 音楽の世界を舞台にした 天才たちの栄光と苦闘…それにしても 音楽の 世界は 凄まじい。消えていった神童たちの その後の方がなぜか気になる、そんな印象の作品だった。2018/04/07
まーくん
96
先年、亡くなられたピアニスト中村紘子さん。まだまだ若かったのに…。彼女が審査員を務めた1986年のチャイコフスキー・コンクールの経過をたどりながら、日本や世界の音楽事情について語る。文章が上手。審査の内情が面白く引き込まれる。ピアノの世界も男性優位(特に西洋では)というのには驚いた。チャイコフスキー・・では、女性の第一位入賞者は出ていないという。複雑な事情からナタリア・トルルを第二位に終わらしたことに痛み覚えるという。世紀最後の’98年大会の頃には女性の第一位が誕生しているかも知れないと期待を込めている。2020/02/16
やいっち
86
中村氏のエッセイ本は好き。『ピアニストという蛮族がいる』や『アルゼンチンまでもぐりたい』などを読んできた。達筆だし勢いがある。ピアニストとして一流なんだろうが(吾輩が評価をするのは僭越)、達意の文章で率直、正直。ユーモアのセンスもたっぷり。2022/07/30
赤とんぼ
22
中村紘子先生のとてもチャーミングで鋭い指摘に、何度も、ハッとさせられました。ここで指摘されている問題は、今でもあると思います。 それでも、西洋音楽を教養主義よりも一種の娯楽主義からとらえる人々は、確実に増えていると思います。だからこその問題も生まれているとは思いますが。(クラシック音楽を聴く人の数が減っていることの根底には、このような、世代によるクラシック音楽への感覚の差があるように感じることがあります) コンクールの内側が少しわかる、とても興味深い本でした。 2017/10/25
HoneyBear
22
訃報を知る。中村紘子さんのご冥福を祈ります。以下転記:チャイコフスキー/コンクールは演奏家にとってのオリンピック。数万時間を練習に捧げ楽器を極めた演奏家たちの凄まじい戦い。その中で入賞を果たし、審査員まで務めた作者の解説は素晴らしい。曰く、リヒテルは尊敬され手本とされるが誰もリヒテルを目指そうとしない。ホロヴィッツを手本にしたら一巻の終わりだが彼のようになりたいと思わないピアニストはいないと。この本を手にYouTube等でいろいろな演奏家の聴き比べをすることが楽しみとなった。(私にはリヒテルが一番。)2016/07/29