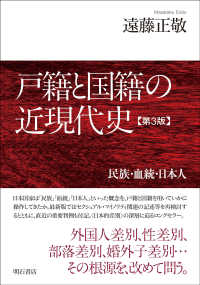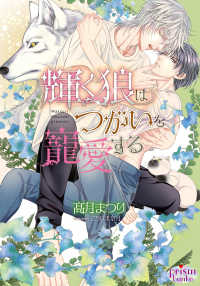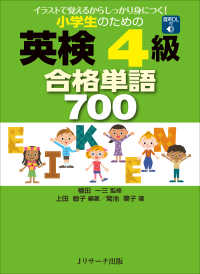内容説明
化身転生者としてチベットの宗教界・政治界における最高責任者となつた14世ダライ・ラマ・隣接する共産中国の度重なる弾圧、インド亡命という苛酷な運命に抗して、釈尊に発する、ガンジーの非暴力政策をつらぬき、平和を希求するチベット民族史の真実を語る感動の自伝。
目次
農夫の息子
悟りを求めて
心の平和
隣人・中国
侵略
共産中国との出会い
弾圧のもとで
インド巡礼の旅
決起
ラサの危機
脱出
亡命、海外流浪へ
現在と将来
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
金吾
23
○チベットに関する一級資料だと思います。領土、国民、主権という国家を形成する三要素を持ちながらも軍事力が乏しいために侵略され独立を失ったチベット、国際社会の脆弱性、独立を失った民族が被侵略国からいかなる扱いを受けるか等、学ぶものは多いです。2022/07/02
肉欲棒太郎
6
重い読後感。本書は、今日にも通じる中国の「帝国主義」を考える上でも必読の書であると思う。興味深いのはダライ・ラマの、毛沢東と周恩来に対する印象の違いで、彼は結局最後まで毛沢東に対するある種の「幻想」を捨て切れなかったようだ。かつて竹内好は大東亜戦争の侵略的側面を評して「侵略はアジア連帯の歪められた表現」だったと述べたが、中国によるチベット「侵略」も同様だったと言えるのだろうか?2016/09/20
wei xian tiang
5
ダライ・ラマ「チベットわが祖国」 中共によるエスニッククレンジングと言ってもいい程のこの50年、チベット民族の苦難は筆舌に尽くしがたい。十四世猊下の人格的魅力もあり、チベット問題は世界的に広く知られている一方、中共による他の少数民族への残虐行為は、「ウイグル族」関係以外ほとんど話題にもされない。日本の読者には、内蒙古での民族浄化、特に文革期の「内人党」取締に名を借りた残虐極まるモンゴル人への虐殺、強姦、拷問その他数々の非人間的行為を捨象して欲しくない。2017/08/02
Sumiyuki
1
高3の時、ダライラマの講演を拝聴した。その時は、宗教なんて下らないって思ってた。けど今になってみれば、宗教の力は凄いと思える。ガンジーについても知りたくなった。社会が社会として成り立つためには、チベットの宗教のような思想が必要なのかな。その思想は、人間の実存の物語なのだと思う。実存の物語は、何でもいいと思うけど、独善的であってはだめ。もしそんな物語を各々がもち、相手を尊重できるとしたら、社会統合も可能なのかもしれない。@あらゆる人間の希望は、分析してみれば、最後には、純粋に、心の平和を求めることである。2011/12/10