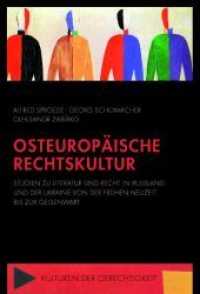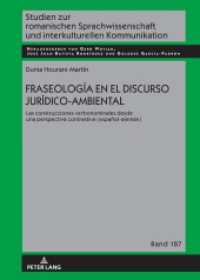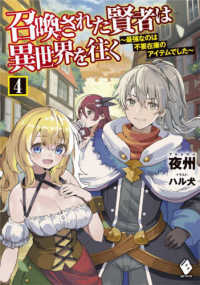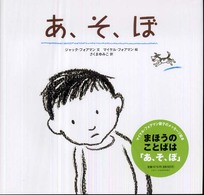内容説明
日本の歴史は、地震の歴史だと言っても過言ではない。人の記憶になく、文書に記述がないからといって、地震が存在しなかったと速断するのは大きな間違いと言えるだろう。本書は、「地震考古学」を確立した著者による、日本歴史を地震の連鎖として描く異色の読み物である。巻末に、東日本大震災に関連して、現在の日本列島と共通点が多い九世紀の地震活動を増補し、地震活動活発期にある日本の備えを考える。
目次
第1章 縄文時代~古墳時代
第2章 飛鳥~平安時代中期
第3章 平安時代後期~室町時代
第4章 安土桃山時代
第5章 江戸時代
第6章 江戸時代末期
第7章 近・現代
終章 二一世紀の地震
増補版のための補遺 東日本大震災のあとで
著者等紹介
寒川旭[サンガワアキラ]
1947年(昭和22年)、香川県に生まれる。東北大学大学院理学研究科博士課程修了、理学博士。通商産業省工業技術院地質調査所および独立行政法人産業技術総合研究所主任研究員を経て、現在、産業技術総合研究所招聘研究員。地震考古学・地震地質学専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
モリータ
13
◆原著2007年刊、2011年5月増補版刊(「東日本大震災のあとで」を補遺)。著者は東北大理学研究科出身、産総研など政府系研究機関の研究員を歴任、専門は地震考古学・地震地質学。◆古代~現代に日本列島で発生した地震につき、①歴史的事柄②文献に見える地震の記録③考古学調査による年代の推定というパターンで記述する。③の液状化で生じる砂脈に注目した年代特定の方法がポイント(コメ引用)。京阪神の歴史についても未知の事項あり(芦屋廃寺等)。ただ、淡々と時系列で事実が列挙されるスタイルゆえ通読して面白い本とは言い難い。2022/03/05
月をみるもの
12
異分野連携の妙を感じられる: https://x.com/bamboo4031/status/18728338037288962622024/12/28
はちめ
7
タイトルそのままの内容、概ね古墳時代以降における本邦の確認できる地震について、主に文献により、補足的に発掘調査により網羅的に記述されている。その網羅性にやや辟易とする感もあるがそのリアリティに圧倒される感もある。当然歴史が進むにつれて記述は詳細を極めることになる。要するに日本に住んでいる以上活断層から自由になれないし、一定の地域においてはかなりの定期制をもって地震や津波に襲われることが確実だということだ。☆☆☆☆2019/06/11
Galilei
6
縄文~現代の阪神大震災まで、各地の地震の遺構を史実を交えて解説。自宅は上町断層の傍で、大阪の地震を時代別に付箋で色分して資料とした。▽大学時代の地質調査で、地質と断層の大家(関空の地質調査等々)指導で、断層地図を片手に実習を行った。葉脈の様に覆う新生代の大阪層群は脆弱なのに、高層建築のラッシュに懸念を深めた。▽本書は地震の詳しい遺構に加え、活断層の活動や要員を地理を踏まえて知る事が出来る。▽神戸での2005年国連防災会議に、海外交流協会で某参加国を迎えたが、スマトラ沖大地震直後の会場は沈黙に包まれた。
こと
6
「聖武の治世に起きた天変地異に対する国政や対応策」について研究してみたいと、この本を読んで考えた。 災害史に興味がある私にとってはとても意義のある本だった。地震考古学という研究目線を持つ筆者のため、用語は少し難しかったが、大いに学ぶことができた。 以前読んだ磯田氏の天災に関する本と似た内容もあった。しかし、こちらの本の方が実地調査が根拠となっているため、信憑性の高さを感じた。2019/03/10