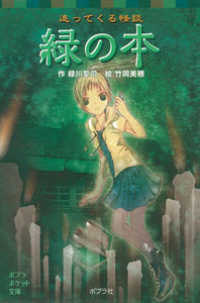内容説明
儒教は宗教というより、単なる倫理道徳として理解されがちだ。古い家族制度を支える封建的思想という暗いイメージもつきまとう。しかし、その本質は死と深く結びついた宗教であり、葬儀など日本人の生活の中に深く根を下ろしている。本書は、死という根本の問題から儒教を問い直し、その宗教性を指摘する。そして孔子以前に始まる歴史をたどりながら、現代との関わりを考える。全体を増補し、第6章「儒教倫理」を加えた。
目次
儒教における死
儒教の宗教性
儒教文化圏
儒教の成立
経学の時代
儒教倫理
儒教と現代と
著者等紹介
加地伸行[カジノブユキ]
1936年(昭和11年)、大阪に生れる。1960年、京都大学文学部卒業。高野山大学、名古屋大学、大阪大学、同志社大学を経て、立命館大学フェロー、大阪大学名誉教授、文学博士。専攻、中国哲学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
harass
54
大田俊寛の宗教学ブックガイド30よりの一冊。儒教の概説書。シャーマンの宗教行為が思想体系として発展した儒教の考えかたや変化の歴史が論じてある。東北アジア人(中国、韓国、日本)の儒教文化圏特有の死生観や血縁主義などの性質がよく分かる。東洋思想の本はあまり読まないが、いろいろ知的興奮を覚えた。葬式のようなありふれた行事や、祖先や家族、学校の先生などへの態度など、古くからの儒教の要素を指摘していく手際に、人類学的な面白さを感じた。これは名著。「本来儒教は、努力すれば聖人(理想的人間)になれるとする。」2017/04/16
syota
27
私は今まで、儒教は倫理道徳であって宗教ではないと思っていたが、著者によればそれは大きな間違いとのこと。儒教は宗教性と礼教性(倫理道徳)の両面を持っており、礼教性が時代にそぐわなくなった今でも、宗教性は根強く残っているとする。その上で、シャーマニズム的な原儒から孔子による体系化、歴代中国王朝との結びつき、朱子による哲学性の付与と、時代を追ってその発展、変化を解き明かしている。著者の研究成果と信念を注ぎ込んだ大変な力作。100%納得するかどうかは別にしても、久々に読書で知的興奮を味わった。2018/05/06
りー
25
白川静さんに触れて以来、原始的な「儒」と現代人が持つ儒教イメージ(お説教的な)のギャップに??と思ってきた。儒教が変容していく過程を歴史背景とともに解説している本で、とても分かりやすかった。①原儒(シャーマン的)②儒教成立(孔子による経典整理)③経学時代(漢~唐、五経博士・科挙)④朱子学(宇宙論・形而上学としての整理)…を経て現代に至る。東北アジアには♪現世は楽しく良いところ♪という大前提がある、という指摘に納得。仏教の考え方と真逆で、あー、これが混ぜ交ぜになって日本に入ってきたのか…と、遠い目になった。2021/08/22
サケ太
20
儒教とは何か、と言われても答えられない。日本の葬儀でその影響が強く残っているとうのは驚いた。儒教というものの、宗教性。〈孝〉という言葉の意味合いも面白かった。宗教で提示されている生命論。日本や中国の仏教とインドの仏教徒の差異なども面白い。儒教の成立過程、変遷。儒教による倫理観。非常に興味深い1冊だった。2022/02/28
スターライト
9
江戸時代以来、日本の風土・慣習・思考に儒教の影響が深く横たわっているのではないか。その教えとはそもそも何?という興味もあって手に取ってみた。著者によると研究者も含めて儒教の倫理道徳の側面から理解されており、宗教的側面が軽視されているという。そのため、宗教としての儒教も取り上げながら、孔子がいかにして一大思想体系として作り上げたか、中国での仏教・道教との争い、日本での需要の仕方、中興の祖としての朱子の業績などを詳述。現代の儒教の動向にも目を配った良書。2022/06/29
-

- 電子書籍
- C0DE:BREAKER(18)
-

- 電子書籍
- 宇宙に学ぶ - 地球の次の時代の文化の…