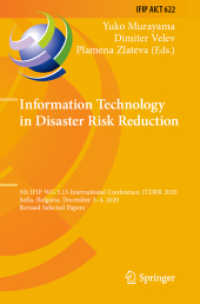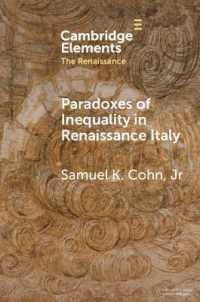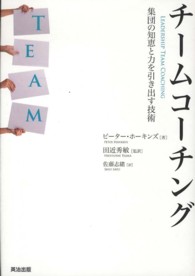内容説明
かつて日本人は自然を愛し自然に対応して生きる民族だった。それがなぜ現在のように自然を破壊するようになったのか。伝統的な自然観との断絶の跡をふりかえり、自然と人間社会とのバランスを崩した土地利用が何をもたらしたかを、水害、水不足、熱公害、大面積皆伐などの具体的事例から追求する。土壌の生産力こそ真の資源であり、それを失った文明は必ず滅亡するという警告は、日本人に深い反省を促さずにはおかない。
目次
序章 自然観の断絶
1 治水の革命
2 不足する水資源
3 水の収奪
4 現代の水思想
5 原点としての明治三十年
6 緑の破壊者
7 失われゆく森林資源
8 土壌と文明
9 農業の近代化がもたらしたもの
終章 新しい道を求めて
著者等紹介
富山和子[トミヤマカズコ]
群馬県に生まれる。1957年、早稲田大学文学部卒業。現在、立正大学名誉教授、日本福祉大学客員教授、自然環境保全審議会委員、中央公害対策審議会委員、林政審議会委員、名水百選選定委員、国際コメ年日本委員会副会長などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ロビン
18
大学時代の恩師が博物館学の授業で紹介してくださった一冊。日本という国が明治半ば頃から、それまで培ってきた伝統的な「自然との共生」「水系一貫」という治水の価値観や手法を放棄し、西洋の「自然を支配する」価値観と技術を上滑りに取り入れ、水と森林と土壌を分断して管理しようとし、そのことによって進んでしまった自然破壊やしっぺ返し的な被害について厳しい調子で警鐘を鳴らしている。エジプトのアスワン・ハイ・ダム建設によって自然環境が激変し発生した被害にはぞっとさせられた。人間は自然に対し謙虚であらねばと思わせられる。2019/12/21
Nobu A
14
冨山和子著書初読。74年初版、10年改版。他著での言及から辿り着いた本書。確か有吉佐和子の「複合汚染」だったような。第一印象は主婦から研究者になり、よく調べた研究の賜物。低水工事と高水工事の違いや経済優先で突き進んだ歴史的背景等、色々と勉強になった。また「47年7月豪雨」は私が5歳の時。今でもよく覚えている。子供用ボートを出して喜んで遊んでいた記憶。大災害との認識は微塵もなく、記憶が歴史と符合した。他方、現在は地球温暖化問題が顕在化し無視出来ないところまで来た。若干偏重的で包括的ではない点が物足りない。2025/03/01
gotomegu
12
スペクタイター「土のがっこう」読書ガイドから。まさしく今の自分にぴったりの内容だった。水の動きが社会に深く関わっているのに、三面コンクリートで固めた川や、汚れた水をただ捨てるためだけに流す暗渠。かつては交通網の一つで、作物を作るにも一番に重要で、災害も川によって起こされた。だから昔は治水に長けた武将が国を治めてきた。明治に、それまでの経験や知識が途絶えた。山林については、今も変わらずに荒らし続けている林政にため息が出る。この本は40年以上前に書かれたのに。2020/12/09
愛奈 穂佳(あいだ ほのか)
5
【ココロの琴線に触れたコトバ】コンクリート時代の今日、日本には依然として都市計画らしいものが存在せず、自然と遊離したかたちでやたらに建設と破壊がくりかえされているのは、自然と対応してこそふさわしかったそうした民族性の上に、異質な素材と技術を運び込んだ末の、分裂症状にほかならない。2015/07/22
taming_sfc
5
富山和子先生による2010年の改版。富山学とも称される富山先生の研究成果が凝集されている。日本の低水から高水への河川事業の歴史的変遷、水・森・土壌をセットで考えるべきとの文明論的環境論は、必読。2010/09/04