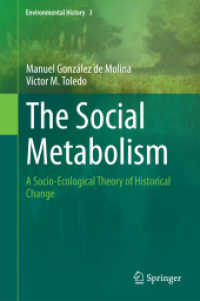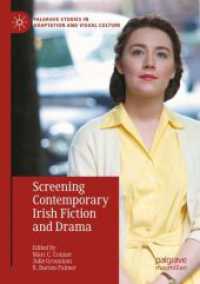出版社内容情報
明治維新に際し、朝敵の汚名を着せられた会津藩は、降伏後いかなる運命をたどったか。維新の裏面史を赤裸に描く回顧録。
内容説明
明治維新に際し、朝敵の汚名を着せられた会津藩。降伏後、藩士は下北半島の辺地に移封され、寒さと飢えの生活を強いられた。明治三十三年の義和団事件で、その沈着な行動により世界の賞讃を得た柴五郎は、会津藩士の子であり、会津落城に自刃した祖母、母、姉妹を偲びながら、維新の裏面史ともいうべき苦難の少年時代の思い出を遺した。『城下の人』で知られる編著者が、その記録を整理編集し、人とその時代を概観する。
目次
第1部 柴五郎の遺書(血涙の辞;故郷の山河;悲劇の発端;憤激の城下;散華の布陣 ほか)
第2部 柴五郎翁とその時代(遺書との出会い;流涕の回顧;翁の中国観;会津人の気質;痛恨の永眠)
著者等紹介
石光真人[イシミツマヒト]
1904年(明治37年)、東京に生まれる。早稲田大学文学部哲学科卒業。1932年、東京日日新聞社(毎日新聞社の前身)に入社。その後、日本新聞会、日本新聞連盟、日本新聞協会勤務を経て、日本ABC協会事務局長、同協会専務理事を務めた。編集にあたった『城下の人』『曠野の花』『望郷の歌』『誰のために』(石光真清著、「石光真清の手記」4部作)は毎日出版文化賞を受賞した。1975年8月逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
118
1971年初出のこの歴史的名著を、これまで読んでなかったことを、心から恥ずかしく思う。戊辰戦争から維新後の差別など、会津人が受けた塗炭の苦しみの心情が切々と語られる。「斗南の荒野」より「人の世の荒野」の辛さに苦しんだ柴五郎氏だが、そんな中でも、野田豁通氏のような人物に出会えたのは、明治という時代の健全さかもしれない。最後は陸軍大将にまで上り詰めるが、中国人民への温かい眼差しを失わない人格者だったと言う。編著者は柴五郎氏を「会津精神の化身、生粋の明治人」と形容する。日本人の精神の美しさがここに昇華している。2024/06/14
森林・米・畑
50
戊辰戦争で会津落城後は箱舘戦争へと目が行ってしまい、会津藩のその後は大河ドラマ「八重の桜」で初めて知った。柴五郎は幼少期に悲惨な結末を迎え、その後の苦労が書かれている。武士の子ながら農業や下働きをし、苦学をした。会津藩出身というハンデを乗り越えて陸軍大将まで上り詰めた。腐る事なく、謙虚さや武士道精神を保つ姿勢は見習うべきだと思った。明治初期の丁髷から散切り頭への過渡期も書かれていて面白い。2024/05/12
nnpusnsn1945
47
幕府側ゆえの悲惨な生活から脱するため苦学し、軍人の道を歩んだ。義和団事件における対応が国際的な評価を得て、陸軍大将までのぼりつめる。後年に陸軍の対中政策を批判し、日本の敗戦までも予言した。中国事情も知っていたが、なおかつ自分が「負けた側」だった身として、辛酸を舐めたからこそわかったのだろう。建軍間もない陸軍の教育事情も伺える。フランス語で教育し、歴史もなぜかフランス史をやるというのは奇妙なものである。なお、当然ながら、薩摩長州に対する反感は大きいのか、文中で度々批判している。2020/12/21
さばずし2487398
36
会津藩士から明治の軍人となった柴五郎の半生を綴った書を纏めたもの。幕末会津と言えば白虎隊が有名だが生き延びた人達にも困窮を極めた凄惨な人生が。父に生き続ける事を鼓舞されつつ犬の肉を吐きながら食べた事、下宿先の主人に酒の席で自刃した家族の事を揶揄された事など、武士としての誇りを教えられた世代がどれだけの思いで敗者として明治を過ごしたか。その環境を乗り切り歴史に名を残した軍人となる道程を支えたのはやはり会津の厳しい武士道精神。柴五郎自体大変謙虚な人柄だったエピが印象的。勝った時でなく負けた後、どう生きるのか。2022/03/12
あきあかね
28
「陸奥湾より吹きつくる寒風、容赦なく小屋を吹きぬけ、凍れる月の光さしこみ、あるときはサラサラと音たてて霙舞いこみて、寒気肌をさし、夜を徹して狐の遠吠えを聞く。」 会津藩士の家系の柴五郎が10歳の時に戊辰戦争が起こり、鶴ヶ城は落城、祖母や母、姉妹を自刃により失う。逆賊·朝敵の汚名を着せられた会津藩自体も67万石から、雪に半年覆われる下北半島の実収7千石の痩せ地に移され、挙藩流罪とも言える状況となった。粗末な家で、炊いた粥も石のごとく凍ったという生活は、塗炭の苦しみという表現が陳腐に思えるほど、凄絶を極める。2019/05/20