内容説明
「ユートピアから科学へ」を乗り越えて「美的=エロス的生活」を目指し、管理社会における人間疎外を批判した暴力・革命論。
目次
ユートピアの終焉―過剰・抑圧・暴力(ユートピアの終焉;学生反乱の目標、形態、展望;過剰社会におけるモラルと政治)
ベトナム―第三世界と大都市の反対派
著者等紹介
マルクーゼ,ヘルベルト[マルクーゼ,ヘルベルト] [Marcuse,Herbert]
1898~1979。ドイツ生まれユダヤ系のアメリカの哲学者。ベルリン大学とフライブルク大学に学び、フッサールやハイデガーの影響を受けヘーゲル哲学を研究。1933年、フランクフルト社会研究所に加入、1934年にナチスから逃れてアメリカに亡命。1940年、アメリカ国籍を取得、その後、ブランダイス大学教授を経て、1965年、カリフォルニア大学教授となる。管理社会における人間疎外を批判、当時、新左翼の教祖的存在となった
清水多吉[シミズタキチ]
1933(昭和8)年、会津若松生まれ。東京大学卒業、東京大学大学院(哲学専攻)修了。東京大学、名古屋大学、静岡大学、早稲田大学、立教大学、法政大学、神奈川大学で講師を歴任。ニューヨーク・ホフストラ大学客員教授、元社会思想史学会代表幹事、現在立正大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
38
遊ぶ(das Spiel)とは、人間のあり方としても、新しい人間学の理念であり、自由を求めてのヴァイタリティーにあふれた要求の成立、展開。疎外された労働という必然性と辛気臭さとに基礎づけられたり、制約されたりすることのない自由(8頁)。著者の言いたいことは、資本主義的工業化と資本主義的技術とが除去されて初めて、工業化と技術一般の諸恩恵が目に見えるもの、現実化されるものになりうるということ(12頁)。自由な社会は、寛容さを必要としない。2016/09/01
ころこ
28
全共闘時代に読み直しといわれていることから相当古く、否定でしか語らないために打ち捨てられ、その古さは全くといって良いほど読まれていないことで現在の読者からはさらに遠ざかっています。今日に文脈が無い方が清々しますが、要は資本主義における疎外の問題を(物凄く全共闘的言葉遣いですが)道徳臭い革命思想によるのでなく、快楽原則=ユートピアの超越性によるということになるでしょうか。真面目さよりも享楽に変革の力が宿るというのは悪くない(否定)と思うのですが。大体、良い悪いの判断を誤ったのが共産主義ですから。2020/10/12
やまやま
8
訳者清水多吉氏のまとめが巻頭にある。同時代の日本の状況を並行して描いているが、日大闘争は50年を経過してなお構造を大学に残存している一方、東大はすっかり軽量化して、それが悪いことではないが、実学に傾いていった気がする。さて、自由と寛容の関係ー自由な社会というものは、寛容さを必要としない、という点や、ベトナム戦争で、合衆国人口の相当の部分が戦争に反対しているが、この世論は戦争を戦争として遂行すること自体に反対なのか、弱体で効果のない戦争の進め方に反対なのかといった問いは今も有効かもしれない。2020/11/01
今川栄吾郎
2
マルクーゼは、個人の意識の高まり(革命を望む者)がある一方で、その者を無力化するような中央集権政府が存在する。人々は自由な社会に生きていると思い、現状に満足している(現代はある程度快適な暮らしが保証されているから)が、それは単に体制内に取り込まれている過ぎず、抑圧されている大勢の人々がいると、指摘し話を展開していく。2018/09/19
-
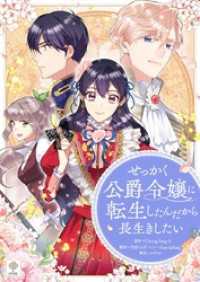
- 電子書籍
- せっかく公爵令嬢に転生したんだから長生…
-

- 電子書籍
- オシリスの天秤 -season2- T…




