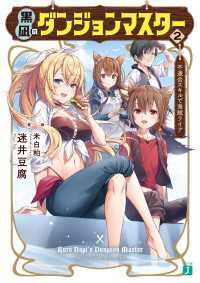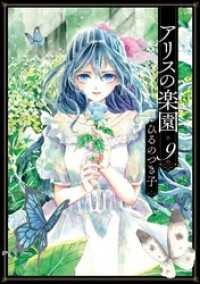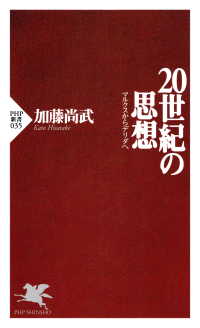内容説明
禅僧が燃やし続けた詩魂に触れれば、真の良寛像が見えてくる―良寛道人遺稿。
著者等紹介
良寛[リョウカン]
1758~1831。江戸後期の禅僧にして歌人、漢詩人。越後(新潟県)出雲崎の名主の長男として生まれる。18歳で隣村の曹洞宗光照寺に入り、良寛と称した。1779(安永8)年、光照寺に滞在した国仙大忍に従って玉島(岡山県倉敷市)の円通寺に赴く。国仙の入寂後、各地を行脚し、故郷に戻ったのは39歳の頃とされる。長く国上の五合庵に住んで無一物の托鉢生活を営み、今日よく知られるエピソードが生まれた。また、その書跡の評価も高く、愛好する人が多い
柳田聖山[ヤナギダセイザン]
1922年(大正11年)滋賀県生まれ。現在、花園大学・京都大学名誉教授。国際禅学研究所終身所員。日中友好漢詩協会顧問
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
rigmarole
12
印象度B-。初良寛で彼の人となりを少々知ることができたものの、本書は全く入門者向けではありません。訳者が「良寛現象」と呼ぶブームで見えなくなった彼の思想やその形成過程を、彼が読んだであろう書籍から典拠を発掘していくことで浮き彫りにしてくという意図は分かりましたが、冒頭の論文と訳注はあまりに専門的過ぎます。特に訳注の出典や連想される文章の多くは漢文であるにもかかわらず訳されておれらず、訳注に訳注が必要なくらいです。本文は超訳とも言える意訳。「百城」を「百万ドルの夜景の町」と訳すに至っては呆れてしまいました。2022/11/28