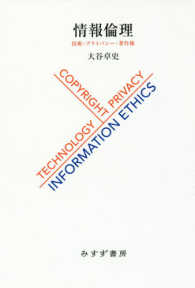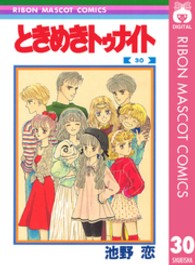出版社内容情報
気候変動、パンデミック、格差、戦争……20万年におよぶ人類史が岐路に立つ今、あらためて我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化芸術、実践活動などの成果をも取り入れて「本来の道」を探る。
そのために本書はまず40億年にわたる生命の歩みを振り返り、生きものとしてのヒトの原点を確認。次に自然を、生きものを、そして我々自身をも手なずけようとしてきたサピエンス史を検証。そこから環境を破壊し、格差を生み出した農耕の“原罪”が浮かび上がり、身近な「土」の重要性が明らかになる。これがレジェンド科学者の結論。
内容説明
気候変動、パンデミック、格差、戦争…人類史20万年の岐路の今、我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化、実践活動の成果をも取り入れて「本来の道」を探る。まず生命誌40億年の振り返り、生きものとしてのヒトの原点を確認。次に自然を、生きものを、そして我々自身をも手なずけようとしてきた人類史を検証。そこから身近な「土」の重要性が浮き彫りになる・レジェンド研究者の結論。
目次
第1部 生命40億年―「私たち生きもの」の中の私(他人事はどこにもない―「私たち」の中の私;始まりは「私たち生きもの」の中の私;体内常在菌叢とウイルス叢があってこその「私」 ほか)
第2部 ホモ・サピエンス20万年―人間らしさの深まりへ(ホモ・サピエンスへの道―まず身体性を;明確になる人間らしさ―認知革命;人間らしさを見つめて―言葉の周囲を巡る ほか)
第3部 土への注目―狩猟採集から農耕への移行と「本来の道」(農耕へ向けて―生命誌による物語を持った上で;農耕社会への移行―拡大志向と格差の始まり;自然の見直しの始まり―有機農業 ほか)
著者等紹介
中村桂子[ナカムラケイコ]
1936年東京生まれ。JT生命誌研究館名誉館長。東京大学大学院生物化学専攻博士課程修了。理学博士。国立予防衛生研究所をへて、71年三菱化成生命科学研究所に入り、日本における「生命科学」創出に関わる。生物を分子の機械ととらえ、その構造と機能の解明に終始する生命科学に疑問を持ち、独自の「生命誌」を構想。93年「JT生命誌研究館」創立に携わる。早稲田大学教授、東京大学客員教授、大阪大学連携大学院教授などを歴任(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
クプクプ
ta_chanko
to boy
nagata
Miyako Hongo
-
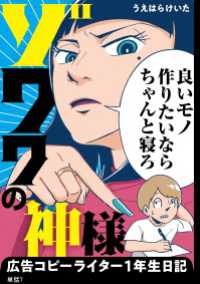
- 電子書籍
- ゾワワの神様 広告コピーライター1年生…
-

- 和書
- 発話解釈の語用論