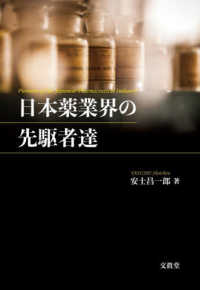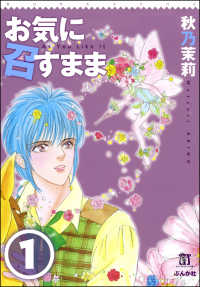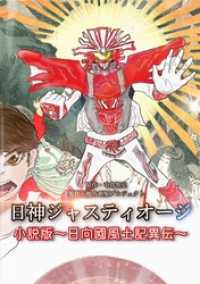出版社内容情報
肉体の性別とは違う性認識を持つことが尊重されるようになってきた。先進的に見えるが、じつは日本の古典文学には、男女の境があいまいな話が数多く存在する。
男同士が恋愛仕立ての歌を詠み合ったり、経済力のある姫が一族を養う。武士は泣き、女将軍が敵に向かい、トランスジェンダーきょうだいは男女入れ替わってすくすく成長――。太古の神話から平安文学、軍記もの、江戸川柳まで古典作品を通して伝統的な男らしさ・女らしさのウソを驚きをもって解き明かす。昔の日本の「性意識」がいかにあいまいだったか、それゆえに文芸が発展したかも見えてくる。年表作りを愛する著者による「ジェンダーレス年表」は弥生時代から現代までを網羅。
内容説明
最近は肉体の性別とは違う性認識を持つことが尊重されるようになってきた。先進的に見えるが、じつは日本の古典文学には、男女の境があいまいな話が数多く存在する。太古の神話から平安文学、軍記もの、江戸川柳まで、古典作品を通して「伝統的な」男らしさ・女らしさのウソを驚きをもって解き明かす。昔の日本の「性意識」があいまいだったゆえに文芸が発展した、という一面も見えてくる。年表作りを愛する著者による「ジェンダーレス年表」は弥生時代から現代までを網羅。
目次
はじめに 日本の文芸はジェンダーレスであふれている
第1章 男女の境があいまいな国―男も出産、女も立ちション
第2章 むしろ女が優位だったかもしれない太古・古代―政治も経済も男女同格
第3章 夫婦別姓、核家族、シングルマザーだらけの古代・中世―「伝統的な家族」とは
第4章 性を重視すると、結婚観はゆるくなる―二度三度の離婚や再婚は当たり前
第5章 LGBTもすべて認識されていた前近代―盛んな男色に宣教師もびっくり
第6章 女々しい男、雄々しい女―男も泣くべき時に泣くのが日本の伝統
第7章 軽んじられた弱者の「性」と「生」―ネグレクトや子殺し、性虐待の多さも
おわりに 「伝統的」のウソと、未来へのメッセージ
著者等紹介
大塚ひかり[オオツカヒカリ]
1961年神奈川県生まれ。早稲田大学第一文学部日本史学専攻卒。古典を題材としたエッセイを多く執筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
さとうしん
めえめえ
lovemys
tsubomi
Aby